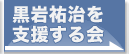
HOME > これまでの著書・コラム > 看護について
物事には潮時というものがある。私は今こそ戦後50年近く置き去りにされてきた准看問題に決着をつける時が訪れたと見ている。
今年の4月から厚生省では「少子・高齢社会看護問題検討会」が開かれ、今後の看護職の在り方について年内に結論を出す方向で検討が進められてきた。この中で准看制度についても議論が行われているが、廃止にむけた報告書がまとまり保助看法(保健婦助産婦看護婦法)改正案の具体案が提示されれば、半世紀にわたる看護界の悲願が実現することになるにちがいないのである。
私はナースのイメージを高めるためのキャンペーンを、番組や出版、講演などを通して4年間にわたって継続してきた。それはナースの3Kイメージが強調され過ぎたことが、かえってナースの働く環境を悪化させていると感じたからであった。すでに本書でも「医療現場のタブー"准看"問題に斬り込む」(1991年8月号)「准看問題なぜ動かぬ厚生省」(1992年1月号)、そして拙著「ナースたちの朝」(講談社)でも准看護婦制度の矛盾点について指摘してきた。
しかし人々の意識に対する働きかけだけでは問題の根本的な解決にはなりえない。そこで制度変革のチャンスが訪れようとしている今こそ、私は改めて具体的変革に向けての提言を行う必要性を痛感しているのである。日本の看護制度最大の問題は准看制度にある。私がナースということばを使ってあえて看護婦という表現を避けているのは、准看護婦は資格上は看護婦とは違うからである。
看護婦が国家資格であるのに対し、准看護婦は都道府県知事の認定資格にすぎない。教育レベルも看護婦が高卒3年なのに対して、准看護婦は中卒2年である(現実にはほとんどが高卒)。ところが現場では准看護婦と看護婦は同じ仕事をしている。つまり仕事は同じで給与待遇面だけ違うというところが、准看制度が安くて使いやすい労働力を確保するためと言われる所以であり、この制度の最大の問題点である。例のアルバイトスチュワーデスが安くて使いやすい労働力を確保するために導入されようとしているのに、実によく似ている。看護職の45%を占めるこの准看護婦の存在は看護の労働現場に差別の構図を持ち込み、看護職全体のステータス向上を阻み続けてきたのである。アルバイトスチュワーデス導入により、スチュワーデスのステータスが下がるのではないかとスチュワーデス自身の中から懸念の声が上がっている。働く者の立場からは当然の声と言えるだろう。
このような矛盾だらけの准看制度を持つのは日本以外、中国、タイなどごく限られている。アメリカやカナダ、スウェーデンなどにも准看護婦はいるが、それは看護婦と明確に業務上のレベル差があり、看護婦の業務を肩代わりするような存在ではない。イギリス、フランス、オーストラリア、韓国、フィリピンなどはすでに看護職は一本化されている。看護職の一本化は世界的潮流と言えるが、イギリスが准看制度を廃止したのは今から5年前のことで今は新しい制度への移行過程だと言う。日本の看護制度変革の千載一遇のチャンスにあたり、このイギリスの経験からに日本はいったい何を学ぶべきなのだろうか。私は急遽ロンドンに飛び、変革の背景を探った。
9月半ばと言うのにロンドンはもうすっかり秋の気配であった。滞在中は毎日雨で、ロンドンの冬特有の重い雲はすでに垂れ込め、街は灰色に煙っていた。吐く息は白く、コートを着ている人さえ少なくなかった。私たちが訪れたロンドン市内のホメトン病院は、建物自体から歴史の重みが伝わってくるような風格を感じさせる病院であった。門構えの一角にナース専用口があり、ナースや看護学生が盛んに行き来をしていた。彼女たちはフアッションにしてもヘアースタイル、化粧の仕方にしても概して地味な感じで、ピカデリーサーカスを闊歩しているフアッショナブルなロンドンっ子とは明らかに違っていた。敷地内に建ち並んだ病棟のひとつ、その5階が私たちの取材の現場となった内科病棟であった。6つのベッドごとに壁で仕切られたブロックがナースステーションを中心に5つあって、すべてが開放されていた。全体が一つの部屋になっているため、看護する側にとっては常に全体に目が届いて看護しやすくなっていた。ただ患者にとってはゆっくり落ち着くという環境ではなさそうだった。
24人の入院患者に対して15人のナースが3交替制で勤務していた。イギリスの100床当たりの看護職員数は平均58・6人であるから、平均よりもこの病棟はやや多めであった。ちなみに日本は43・1人、アメリカでは56・0人である。
人数的には少しゆとりがあるはずなのだが、勤務の状況を見ているととてもそんな風には見えなかった。食事の世話から排泄の介助、薬を配ったり点滴の交換、詰まった痰の吸引など、ナースたちは常に患者の間を行ったり来たりで、一息つく間もないほどであった。
ナースたちをよく見ると、ベルトの色が違っているのに気がつく。青が正看護婦(Registered Nurse)で、緑が准看護婦(Enrolled Nurse)、黄色が正看護婦を目指して勉強中の准看護婦である。それ以外にも青い制服を着た看護学生、白いガウンを着た医学生、オレンジの制服を着たヘルスケア・アシスタントらがナースの仕事を手伝っていた。ナース15人中13人が正看護婦で、緑ベルトと黄色ベルトの准看護婦が1人ずつであった。准看制度自体は廃止されたが、まだその移行過程にあるということが現場を見るとよくわかる。
イギリスのナースの教育レベルは日本とほぼ同じで正看は3年、准看は2年である。そもそも1919年に看護婦法が施行された時点では正看だけの1種だったが、第2次大戦中の極度の看護婦不足を補うために、1943年看護アシスタントとして准看を育成することになった。日本が戦後の看護婦不足を補うために、准看制度を導入したのによく似ている。 ただ日本とは違い正看と准看の業務上の差はあって、准看は正看のアシスタントとして位置付けられていた。ただしそれはあくまでも制度上の事であって、実際の現場レベルでは必ずしも明確に線引きがされていたわけではなかったようだ。
「実際には病棟に正看がいない時には准看が代行せざるをえないですから、結果的には准看も正看も同じ仕事をするようになっていましたね。」
イギリスのナースが全員登録されている管理組織、UKCC(英国看護中央審議会)の登録官補佐マーガレット・ウォレス女史はそう語った。ところがそのことが逆に准看廃止の議論につながっていったのだと言う。
「1980年代に入って医療の質が向上してくると、正看からは自分たちと同じレベルの仕事を准看に任せるのは問題だという指摘がなされるようになりました。また准看からも今やっている仕事は自分たち本来の仕事ではなく、負担が重すぎるという不満の声が出てくるようになりました。こういった声を受けて21世紀に向けて看護はどうあるべきなのか、それにふさわしい教育の在り方はどうなのかが検討されることになったのです」
そこで1985年に看護教育新制度調査委員会が設けられ、当時オックスフォード大学の教育研究局長であったハリー・ジャッジ氏が委員長になって看護教育の現状についての調査研究が進められた。1年後に出された「ジャッジリポート」では看護教育の質的向上の必要性が強調されていたが、それをもとにUKCC(英国看護中央審議会)が2年間かけて「プロジェクト2000」という提言をまとめあげた。
そこでは准看教育を廃止し看護教育の一本化を図ることが明示されていたが、これが変革の具体的指針となったのである。保健省は1988年にこの「プロジェクト2000」を採用し、翌年9月から実施に移すことになった。
これにより全国の准看養成コースはいっせいに正看養成コースに切り替えられ、准看護婦の多くは正看護婦への移行プログラムを受講することになった。「プロジェクト2000」以前にも1年4カ月の移行プログラムがあったが、働きながら学べるコースがなかったため、受講者はあまり多くはなかった。それが「プロジェクト2000」により、1年間(52週)の全日制の移行プログラムと2年間の夜間コースが設けられた。しかも本人の経験や技量が査定されて、52週分の内3分の2までは免除されるとともに、通信教育も採用されるなど、実態に即した改革が行われたのである。
これがイギリスにおける准看制度廃止の背景であるが、このような大変革をもたらす最大の原動力は「ジャッジリポート」だったと関係者は口をそろえる。このリポートがなぜにそれだけの大きな力を発揮したのか、同じように看護制度の一本化を目指す日本が学ぶべきポイントがそこに凝縮されているように思う。
その第一は看護制度の変革を"看護教育の変革"という視点からとらえたことである。正確には准看制度を廃止したというより准看教育コースを廃止したというのが正しい。准看レベルの教育では医療看護の現場のニーズに応えられないという危機意識から議論を始めた点が、より多くの人々の共感を生むことにつながったのである。
日本の場合は医師にとって安くて使いやすい労働力としての准看制度の矛盾点に焦点が当てられ、准看問題は主に労働問題として論じられてきた。労働現場における差別の構造が組合闘争の中で厳しく質されるというパターンが続いてきた。それが結果として変革にとってマイナスに働いてきた面があったかもしれない。 イギリスの場合はナースの75%が公務員であり、日本のように医師が病院を経営しナースを雇うという関係ではないから、ナースの賃金が安いか高いかは医師にとって関係のないことである。そのため一概に同列に論じるのはふさわしくないかもしれないが、そのイギリスでさえ医師会の中からは看護教育の変革に反対の声が起きていたと言う。
「医師の中にはナースの教育レベルを上げると、アカデミックに偏り過ぎて臨床の現場がおろそかになるのではないかと心配をする人たちがいたんです。学究的な知識よりも実務上の技能を重視すべきじゃないかと言うんですね」
英国看護協会の教育顧問ドロシー・スペンサー女史はそう語った。
これと同じ議論は日本の医師会の中にもあるが、それは基本的にはナースは医師のアシスタントで十分だという意識が背景にあるものと言っていいだろう。医師の教育レベルが高いからと言って医師が臨床を嫌がるということはないのと同じである。臨床を嫌がるナースがたくさん出てくるような教育は、決してレベルの高い教育とは言えず、そんな教育に変革するはずがないのである。
「反対した医師も今では私たちの考えを支持してくれています。結果的には優秀なナースが育ってきたんですから」
スペンサー女史は誇らしげにニッコリと微笑んだ。
「ジャッジリポート」の注目すべき第2のポイントは、看護教育についての調査研究であるにも関わらず、看護関係者ではないハリー・ジャッジ氏が取りまとめの責任者になったことであった。ジャッジ氏はオックスフォード大学の教育研究局長であり、この調査を任されるまではナースの世界については、全くの素人だったと言う。
スペンサー女史はジャッジ氏と仕事を始めた当初のことをこう語った。
「ジャッジ氏は教育の専門家ではあっても看護のことはほとんどご存じなかったんです。それで彼がこの調査を開始した当時は、探るような目付きで色々な質問をなさるものですから、お話ししていても気詰まりでした。でも結果的には看護関係者でないからこそ見えることがたくさんあって、ああいった報告書がまとまったのではないでしょうか」
「ジャッジリポート」は看護教育が専門分野に偏り過ぎていることの弊害を指摘し、もっと幅広い一般教養を身につけられるものに変えていく必要性を強調したものとなっている。ジャッジ氏が看護の素人であればこそ、看護教育と一般学生の教育との客観的な比較ができたのである。看護教育の現場しか知らない専門家には、なかなか他の世界は見えないものである。
その点についてジャッジ氏自身は次のように語った。
「私はこの問題について"インサイダー・アウトサイダー"というような立場でしたね。つまり教育問題ではインサイダーだけど、看護問題ではアウトサイダー。でもそれが逆に公平な判断につながったのではないでしょうか。」
結果的に「ジャッジリポート」が看護制度の変革にまでつながっていったことについて彼自身は次のように語った。
「病院実習を義務付けられている看護学生は病院の中では貴重な労働力と見なされ、一般学生と比べて決して恵まれた状況ではありませんでした。それだけに私たちがナースの意識を調査すること自体、彼女たちにはきっと何かが変わろうとしているのだという期待感が広がったようでしたね。それで私たちも『今こそ変革の時だ』と強調したリポートをまとめましたが、それがきっかけとなって変革に向けて動きだしたことは間違いないんじゃないでしょうか」
日本ではナースの問題をナースの間だけで議論するという傾向が強かった。そのために同じ議論がいつも同じ人たちの間で繰り返されるばかりで、少しも広がりを持たず、変革のエネルギーにはつながっていかなかった。その典型が准看問題であった。看護関係者でない人物が看護変革の道を切り開いていったイギリスの例は、日本にとって大いに参考になるはずである。
さてこれまでの取材を通じて日本の准看問題を解決する具体的方法について私なりにまとめてみたい。
第1にイギリスと同様に准看制度廃止を准看教育廃止と位置付けることである。それがこの問題を神学論争から開放し最も現実的な解決策につなげていく鍵になると私は思う。そして教育レベルを最低高卒3年の看護教育に一本化し、新しく誕生するナースは全員正看となるようにする。このためすべての准看養成学校を正看養成学校に切り替えることになるが、制度移行期の特別措置で学校の設置基準を緩和したり、積極的な国の財政援助は必要となるだろう。
第2に今の准看が正看になりやすい環境整備を早急に行う必要がある。准看から正看への移行については今の進学過程(2年?3年)を基本にしつつ、それぞれの技量に応じて便法も工夫すべきである。近く通信教育が導入されることになっているが、これは大いに活用できるはずである。
准看廃止によっていきなり看護婦の名称に統一すべきという主張があるが、私はそれには賛成できない。現に苦労しながら進学過程を経て正看になった人たちが数多く存在する中で、それはかえって不公平になると思うからである。
第3に准看から正看になる意志のない人は准看のままでこれまでどおり、働けるようにすべきである。イギリスにおいても准看の30%は移行の意志がなく、これまでどおりの状態で働いている。決して全員に正看になることを強制すべきでないし、なし崩しで彼女たちを正看にするのもよくないと思う。
第4に高校の衛生看護科出身の生徒は卒業と同時に准看の資格を得るようになっているが、ここにはこの際触れる必要がない。なぜなら現状ではそのまま就職せずに、進学過程や看護大学に進む生徒が多いからである。ここに手をつけようとすると、准看廃止問題は複雑になり過ぎて手がつけられなくなってしまう。あくまで現実的な解決策を考えるべきである。 第5に3年過程の看護学校をすべて短大扱いにすべきである。今は同じ3年過程なのに専門学校と短大に分かれているのはおかしい。本来はすべて短大に一本化すべきであるが、せめて短大卒に見なすという方法が考えられてもいいのではないか。
以上の5点が私の准看問題解決のための改革案である。これでは准看が医療現場からいなくなるのは何十年も先になるかもしれないが、私はそれでもいいと思う。現に医療看護の最前線で37万4千人もの准看が働いているという現状を忘れるわけにはいかない。准看廃止、准看廃止とお題目のように唱え続け、いつも医師会に黙殺され続けてきたこの問題に決着をつけるには、あくまで現実的な解決策を考えるべきである。看護の教育レベルを上げるという議論に持っていくことが、医師会も表立って反対しにくくなる最善の方策なのである。
私もハリー・ジャッジ氏と同様、看護関係者ではない。だからこそ逆に大きな変革のエネルギーを生み出せるということもあるはずである。そういった思いでいよいよ大詰めを迎えようとしている保助看法改正の作業を、しっかりと見守っていきたいと考えている。