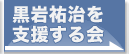
HOME > これまでの著書・コラム > 看護について
医療保険改革や介護保険法案など、患者にとって自己負担の増える話が続いている。介護、看護を必要とする人がたくさんいるにちがいない超高齢化社会を前にすれば、ある程度の負担増もやむをえないだろう。しかし、まず今の医療費の無駄をなくすところから始めてもらわないと、私たちもすんなりと負担増を受け入れる気にはなれない。そのために診療報酬体系や病院の在り方の見直しなどが求められているが、看護力が医療費削減の鍵を握っていることはあまり注目されていない。
日本は患者の入院期間の長さにおいて、諸外国を圧倒している。平均在院日数はアメリカの4倍の34・6日(1994年)にも達している。国民皆保険制度があればこそ、ゆっくり入院していることもできるのだろうが、入院期間が長いのは患者にとって決してありがたいことではない。しかも本来はもっと早く退院できる人が長く病院に留まっているとしたならば、これは医療費の無駄と言わざるをえない。 実はアメリカでも入院期間を短縮させるためのさまざまな努力が行われていた。その中で最も効果の上がったのが看護の質を向上させることだったと言う。 「週間社会保障」の9月23日からの一連のリポートがそのあたりを詳細に伝えている。
「全員が看護婦で構成されるICUの方が、看護婦、准看護婦、看護補助者の混合構成のICUよりも、死亡率は16〜41%の範囲で低くなっている。全員が看護婦であると、患者の合併症を予防でき、在院日数も短縮され、病院全体のコスト削減に効果的に働き、さらに患者の満足度も高い」 自ら独自の看護技術の開発に取り組んできた筑波大学の紙屋克子教授も、そのリポートの中で看護力の充実によって、「在院日数を約70日から25日に短縮させた」と証言している。 2時間ごとに重症者の体位を変えることを徹底させることなどによって、床づれができないようにして、その結果、患者は早く退院できると言うのである。
私も紙屋さんの看護技術を体験したことがある。ベッドに横たわった私の体位を変えたり、起こして椅子に座らせるという一連の技はまるで魔法のようだった。最小限の力で最大限の効果を上げるその技術は、合気道のそれに似ていた。看護者だけでなく患者にとっていかに負担が少ないか、私は身をもって体験することができた。
ドクターは手術が成功すればそれで満足だろうが、患者にとってはそれから後の方がよほど大変である。術後の痛みの克服から食事の再開、リハビリ、そして退院まで、つらい闘いが待っている。それを支えるのがナースであり、その看護力が充実していればいるほど早い退院が可能になるというのは、患者の実感としても理解できることではないだろうか。
今、厚生省の「准看問題調査検討会」で「准看養成の停止」を決めることができるかどうかの大詰めの段階に入っている。
ナースがドクターのお手伝い役であればよかった時代は終わった。在院日数を減らす潜在的な力を持ったナースというのは、日本の医療を21世紀型に変革していくために、最も重要な使命を担っていると言えよう。
准看護婦(士)が戦後の医療を支えてきたことは高く評価しなければならない。しかし、これからナースが果たさなければならない仕事の大きさを思う時、2年間の准看養成教育ではあまりにも不十分だということはすでに議論の余地のないところである。
准看養成はこれまでその主なる担い手であった医師会にとっても、大きな負担だったはずである。各新聞論調も准看養成の停止を求めることで一致した今となれば、医師会も准看養成の負担から逃れられる最大のチャンスでもある。
医師会の中には未だに准看を今のまま存続させたいとこだわっている人もいるようだが、患者の立場でその意見に賛同する人はいない。彼らは准看養成が停止されたら、中小病院や診療所にナースが来てくれなくなることを心配しているようだが、それは被害妄想というものである。
21世紀はいかにして地域の医療を充実させるかが、最大の課題である。国民医療総合政策会議もかかりつけ医を最重視する方向を打ち出しているように、21世紀は開業医の時代と言ってもいい。
新しい時代の開拓者たるべき開業医にとって、訪問看護などを担える優秀なナースをパートナーにすることは必要不可欠である。いつまでもナースをお手伝いさん感覚で見ているような前時代的な開業医だけが、准看制度を温存させようと考えているのであって、彼らの横暴によって時代の流れが止められるとするならば、それは国民医療改革への敵対的行為と言わざるをえない。
日本の看護制度は今、戦後最大の変革の時を迎えようとしている。質の高いナースの供給体制を整備しようとするその変革は、なによりも私たち患者にとって歓迎すべき流れなのである。