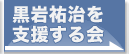
HOME > これまでの著書・コラム > 看護について
平成8年12月20日は、日本の看護界の長すぎた戦後が終わった歴史的な日となった。厚生省の准看護婦問題調査検討会が准看養成停止を求める報告書をまとめあげたのである。「お礼奉公」「現代の女工哀史」など、およそ現代日本に似つかわしくない言葉で語られてきた准看問題が、いよいよ決着の時を迎えたのであった。
検討会で最終報告案が了承された瞬間、委員の中から思わず拍手が巻き起こったと言う。検討会の場で拍手が起きるなどというのは異例のことであり、いかに日本の看護界にとって革命的とも言える重大な出来事だったかがうかがい知れるだろう。
私も平成3年にフジテレビのFNNスーパータイムで、准看制度の廃止を訴えるキャンペーンを始めて以来、「感動の看護婦最前線」などの番組を通じて6年間にわたってこの問題に取り組んできた。よくこんな地味なテーマにいつまでもこだわっているものだと揶揄されることもしばしばだったが、それ自体は一見地味に見えても、日本の医療が21世紀型に変革できるかどうかのかかった最重要テーマであると私は確信していた。
本誌においても「医療現場のタブー・“准看”問題に斬り込む」(平成3年8月号)、「准看問題なぜ動かぬ厚生省」(平成4年1月号)、「准看問題今こそ決着のとき」(平成6年12月号)と、3度にわたって寄稿してきた。それだけに今回の決定は特に感慨深いものがあるが、そこに至った背景を検証しながら、この報告が21世紀の看護・医療の在り方にとってどのような意味を持つものなのかを展望してみたい。
准看制度ができたのは昭和26年。もともと厚生省では、高校卒業後3年の専門教育を必要とする看護婦に一本化する方針を決めていたが、医師会の強引な政治工作によってひっくり返されたのだった。当時の女子の高校進学率は37%しかなく、高校卒業を最低条件にすると数のニーズに応えられないだろうという医師会の主張に看護側も十分な反論ができなかった。そして中学卒業後2年の教育で資格を取れる准看護婦が当面の措置として作られたのだった。
看護婦は国家資格、准看護婦は知事の認定資格と明確に区別された。同種の業務に2種の資格があること自体は、弁護士と司法書士の例を見ても明らかなように何の問題もない。しかし、もともと数合わせで作られた制度であったがために、看護婦と准看護婦に同じ業務が認められたことが、看護の現場に複雑な影を投げかけることとなった。同じ仕事ができて給与待遇だけに差があるということは、看護婦を雇う側にとってみれば、准看護婦は安くて使いやすい便利な労働力ということになる。それゆえ、看護界が一貫して制度廃止を訴えてきたにもかかわらず、医師会はこの制度を徹底的に死守しようとしたのだった。 21世紀に向けて、より専門的で高いレベルの看護の提供を目指そうとする日本看護協会にとっても、准看廃止はどうしても越えなければならない最初で最大のハードルであった。しかし、日本医師会の猛反対の前に連戦連敗を余儀なくされ、一歩も前進できない状態が長く続いていた。
平成3年、視聴者の准看護婦さんからの一通の手紙がきっかけとなってこの問題に取り組むこととなった私であったが、これまでの准看問題をめぐる議論を整理してみて、そこに患者の視点が全く欠落していることを知り愕然とした。
教育レベルも資格レベルも違う看護婦と准看護婦に同じ業務が許されるということは、患者の立場から見ればとても納得できることではなかった。そしてこの制度自体が看護全体のレベルアップに大きな障害となっているとしたら、最も大きな被害を被っているのはむしろ患者の方であり、准看問題は看護婦の問題というよりも患者の問題と言うべきなのではないかというのが私の結論だった。
患者の視点から准看問題を斬ることできっと解決への糸口が見つかるにちがいないということで、私はテレビと活字を使ったキャンペーンを始めた。それは私にとっては救急救命士誕生に結びついた救急医療キャンペーンのノウハウをそのまま活かしたものだった。
救急救命士の時も、「医師以外の医療行為は認められない」という日本医師会との激しい闘いであったが、准看問題は診療所や病院の経営にかかわる問題でもあって、日本医師会の反対は比較にならないほど激しかった。それが平成6年、厚生省の少子・高齢社会看護問題検討会で、期せずして准看問題が議題に上ったことから、一気に解決に向けて動き出すのではとの期待感が生まれた。私が本誌に「准看問題今こそ決着のとき」(平成6年12月号)を書いたのは、そういった流れを十分に意識してのことだった。
その時、私が提言したのは、看護界が長年主張してきた「准看制度廃止」の看板をいったん降ろして、「准看養成停止」によって実を取れということであった。つまり准看養成を停止することによって、新しい准看は出て来なくなる、それと同時に今の准看を再教育して看護婦にどんどん引き上げていく、そうすればやがて准看はいなくなり、看護婦に一本化されていくというのである。それはイギリスが1989年に准看問題を克服した時に採用した手法だった。
医師会の抵抗の激しさからして、「准看制度廃止」で展望が開けるとはとても思えなかった。それよりも「准看養成停止」の方が抵抗は少ないだろうし、実現可能性の高い方策であると思ったのである。しかも「准看養成停止」は看護の教育レベルの向上を目指そうということであって、患者にとっても理解しやすく、共感をえられやすい改革であるにちがいなかった。 しかし、検討会では地方の医師会からの猛烈な突き上げにより、結局、問題は再び先送りされることとなった。ただその時、単に先送りしたのではなかったことがその後の展開につながった。准看、ならびに准看学生の実態調査を行うことの了承を取り付けたのであった。それは准看問題決着に情熱を燃やす厚生省の久常節子看護課長の執念であった。
「准看問題なんて言うが、実態を調べたことがあるのか。一部のことを組合やマスコミが大きく取り上げているだけのことではないのか」
検討会の中で日本医師会の代表からそんな発言が飛び出したと言う。これは半世紀近く看護界が訴えてきた問題そのものを全否定するような発言である。日本看護協会、医労連などはこれまで独自に調査してきた結果を示した。しかし、日本医師会はあくまで国のデータにこだわった。国としての調査がこれまで行われていなかったことを知った上での、嫌がらせとも言える態度であった。
久常課長はそこを逆手にとって国が実態調査を行うことを提案して、了承を取り付けたのである。日本医師会もそれには同意せざるをえなかったが、「実態調査」ということばを使うことには抵抗を示したと言う。結局、「実態の全体把握」ということばとして、報告書に盛り込まれたのであった。
平成8年6月、調査結果が公表されたが、その内容は予想をはるかに越えるきびしい内容であった。
「准看護婦・非近代的実態明らかに」(読売)
「こき使われる准看養成学校生徒」(東京)
「無資格で注射・採血、2割・『お礼奉公』も横行」(朝日)
各紙の見出しを見るだけで、准看護婦の悲惨な実態が伝わってくるが、何よりも衝撃的だったのは、准看学生が注射や採血などの医療行為をしていることであった。注射は18%、採血は22%の学生が行っていると答えていた。准看学生とは准看護婦になるために勉強中の学生であって、まだ無資格の身である。無資格者が医療行為を行うのは明らかな医師法違反である。しかも准看学生の23%が夜勤をしており、3・6%は月に7〜8回もの夜勤をこなしていた。学校に行きながらそんなに夜勤をすると休みがなくなってしまうのではないかと心配にもなるが、それもデータ上にはっきりと表れていた。1カ月のうち、勤務も学校もない完全な休日は1日もないと答えた学生が4・7%もいたのである。
「昼間は学校に行き、帰ってくるとそのまま毎日、次の日の朝まで夜勤をさせられました。学校が休みの日は朝から勤務です。もちろん注射から何からすべてやっていました」
私が直接取材したある准看護婦は、准看学生当時を振り返ってこう語った。
「じゃあ、いつ寝てたの?」
私ならずともそう聞き返しただろう。
「ベッドでちゃんと横になって寝るということはあまりありませんでした。それでもなんとかなったのは、やはり若かったんですね」
そんな非人間的な労働がこの現代日本に存在していること自体、にわかには信じられない話だったが、調査結果にはっきりとその実態が浮き彫りになっていたのである。過労状態にあると答えた学生は49%、体調を崩しやすいと答えたのが41%、20歳前後の女性の現状としてはどう見ても異常な世界であった。
しかも彼女たちの半数以上が奨学金を受けており、そのうちの8割が卒業後、奨学金を出した医療機関で2年から3年の勤務が返済免除の条件とされていると答えていた。勤務条件がどんなに厳しくても、現実には病院を離れられないように金でがんじがらめになっており、これが「お礼奉公」と言われる実態であった。
「授業中うとうとしている准看学生は多いんですね。でも叱る気にはなりません。彼女たちの置かれている状況を私たちもよく知っていますから」
准看学校の教員からはそういった話を何度も耳にした。調査でも75%の教員が「学生は勤務で疲れている」と答え、77%が「学習意欲の低い学生が多い」と感じていた。3年で3000時間の看護婦教育に対して、准看教育はもともと2年で1500時間しかないのだが、単に量的な問題だけでなく、質的にも大きな問題を抱えていることがわかる。
それだけ疲れている准看学生が看護婦代わりに働かされているという現状を、患者である私たちはこれまで黙って受け入れてきたことになる。この問題がいかに病院の経営上の論理だけで語られ、患者側からの視点が欠落していたかがよくわかるのではないだろうか。
17%の准看学生は夜勤の時に看護婦など有資格者と一緒ではないと答えている。通常でも夜勤はスタッフの数が少ないだけに、ひとりひとりにかかる責任は重い。看護婦にとってもより神経を使う勤務であるのに、無資格者だけで夜勤をさせるというのは、病院という名に値しない暴挙といわざるをえない。私は患者の立場からしてこういった現状にはっきりとノーと言いたいと思った。
もともとは准看護婦の実態調査だったのだが、調査の結果、違法行為が日常的に行われているという日本の医療のお寒い現状が浮かび上がったのである。これで日本医師会が准看制度を死守する大義名分は完全に失われた。「准看養成廃止」に向けての流れはこの調査によって決定的になったのである。
これは以前にも本誌に書いたことだったが、イギリスで「准看養成廃止」のきっかけを作ったのは、オックスフォード大学の教育研究局長だったハリー・ジャッジ氏だった。彼が委員長として看護教育の実態を綿密に調査してまとめた「ジャッジリポート」が、看護教育改革の必要性を国民に痛感させ、変革への流れを作り出したのである。彼が教育学の大家であって看護の専門家ではなかったことが、逆に調査結果への信頼性を高め、大きな影響力を持ったのだと言う。
実は今回の検討会では、日本版ハリー・ジャッジとも言うべき人物が登場していたのだった。それは東京大学人文社会系研究科教授の似田貝香門氏だった。似田貝氏は市民運動の調査分析が専門であり、看護の世界についてはジャッジ氏同様、全くの素人だった。それゆえ准看問題そのものも純粋に第三者の立場から、先入観なしに見ることができたのである。根っからの熱血漢である似田貝氏は調査票に書き込まれた准看、准看学生たちの訴えを見て、涙が止まらなかったと言う。
「彼女たちの『助けて下さい』という叫び声が聞こえてくるようでした。今の世の中にこんな人間性を無視したようなひどい話があるなんて・・・今まで全く知らない世界だっただけに、たいへんなショックを受けました」
似田貝氏は医療現場の底辺に戦後からずっと封じ込められていた准看、准看学生たちの思いを、自らの手で公にしていくことに歴史的意義を見いだしていた。国の依頼だからということで淡々と事務的に行われた調査ではなく、使命感に燃えた新進気鋭の学者が情熱を傾けて取り組んだ調査だっただけに、見事なまでに本当の実態が浮かび上がったのだった。 実は看護界が最も恐れていたのは、実態調査を鳴り物入りで行なったはいいが、正しい実態が結果として出てこないことだった。
その可能性は十分にあった。というのも、准看護婦の多くは医師会の会員が経営する病院や診療所で働いており、准看学生も医師会系の学校で学んでいる場合が多い。つまり、「准看問題など存在しない」と強弁する医師会のお膝下に手を突っ込んで調査しなければならないのである。准看護婦が調査票に書き込む時点や提出の前に、医師からチェックされることだって当然ありうるだろう。有形無形のさまざまな医師会の妨害や圧力が予想されたのである。
万が一、そういうことによって事実が歪められ、准看問題が見えてこないような調査結果が出たとしたら、問題を解決しようというすべての作業はそこで停止することになる。准看問題は医師会の言うとおり、現実には存在しないことになってしまうからである。実態調査は看護界にとっても危険な賭けだった。
そこで久常課長は准看護婦や准看学生に対する調査は、すべて調査員が直接訪問して行なうよう指示を出した。全国の1400人余りの准看護婦(士)や、1150人を越える准看学生への訪問調査というのは並大抵のことではない。調査員は本人に記入してもらった後、ただちにその場で封印して回収した。こうして第三者が調査に介入する余地をなくしたのである。回収率86%という数字も驚異的であるが、それだけ熱のこもった実態調査となったのであった。
また、質問内容をどうするかをめぐっての医師会とのせめぎあいも熾烈をきわめた。質問の仕方次第で問題が浮かび上がらないようにすることは可能である。その質問は誘導的であるとか、選択肢が意図的であるなどと、医師会は細部にわたってチェックを入れてきた。特にどんな業務をしているかという点については最後まで折り合いがつかなかった。そこで妥協案として、自由に自分のことばで書き込めるフリーアンサーの形式にしたのだった。
ところが皮肉なことに、これが誰も予測しない本当の実態を浮かび上がらせることになったのである。無資格者の准看学生による医療行為という恐ろしい事実は、このフリーアンサーのスペースに綴られてきたものだった。似田貝氏が救いを求める悲痛な声と感じたのは、まさにこのスペースにびっしりと書き込まれた彼女たちの肉筆だったのである。
フリーアンサーの集計はたいへんな労力を要する作業だったようだが、似田貝氏は調査票を1枚1枚自分の手でコピーしたと言う。彼女たちの思いのこもった調査票の重みを自分の手で感じようとしたのだった。彼の優しさが伝わってくるようだが、そうしてまとめられた調査結果はまさに歴史を変える決定打となったのであった。
准看養成停止への議論が大詰めを迎えた段階で、関係者が最も知恵を絞ったのは准看制度死守を掲げ続けた日本医師会の振り上げた拳をいかにして下ろさせるかであった。誇り高き職能集団である日本医師会のプライドを守りながら、彼らの譲歩を実現するにはどうすればいいかということである。
まず第1に看護界自らも現実的解決に向けて譲歩する必要があった。日本看護協会は平成8年6月の総会で、これまで掲げ続けた「准看制度廃止」から「准看養成停止」にスローガンを変更したが、これはそういう意味で大きな前進だった。
私もその時の総会で行われたシンポジウムに出席したが、会場からは予想どおり「一気に准看制度廃止に行かなければまた問題が先送りされるだけだ」との強硬論が出された。私は「准看制度廃止にこだわるかぎり、あと半世紀、同じ議論を続けることになるのはまちがいない。准看養成廃止以外の解決策はありえない」と断言し、スローガンの変更を強く迫った。これまで准看制度廃止で突っ走り続けた人たちにとっては、苦しい選択であったにちがいないが、日本看護協会は見事、身を切る変革を成し遂げたのである。
第2に准看養成停止を求める世論の圧倒的な流れを作ることが必要だった。日本医師会も日本看護協会に押し切られたというのでは内部が収まらないだろう。しかし、世論の高まりに押されて譲歩したというのであれば、名誉ある撤退は可能になってくるはずである。
平成7年9月、朝日新聞は社説で「『准』看護婦の養成をやめよ」(9月14日)と明確な論調を掲げた。毎日新聞も「時代の流れに逆らえるか」(平成8年5月9日社説)と「准看護婦の養成制度はもう限界」との認識を示した。読売新聞も解説記事で准看護婦制度の問題点についてはしばしば指摘し続けており、この時も2度にわたって医師会と看護界の対立討論のために大きな紙面をさいた。 私も産経新聞に「現実的な准看養成廃止論」(平成7年10月17日夕刊)を投稿したが、何よりも驚くべきは地方紙の論調であった。「准看養成は廃止のとき」(山梨日日新聞)をはじめ、大分合同新聞、徳島新聞、東奥日報、日本海新聞など、各地の新聞がそれぞれの地元の事情を織り交ぜながら、准看養成廃止論を掲げたのである。
これだけマスコミ論調がそろったということは、日本医師会の名誉ある撤退への環境整備は万全とも思われたのだが、この頃から、医師会は不気味な沈黙を守り始めた。嵐が通り過ぎるのを静かに待っていようということのようだった。
そこで医師会対策として第3の道が必要になってきた。それは医師会が准看制度を死守しようとする本音に改めて虚心に耳を傾け、彼らの気持ちを理解しようと努力することであった。
医師会の頑なな姿勢の背景にあるのは21世紀に向けて病院、診療所がうまく経営していけるだろうかという危機感であった。患者の大病院志向がますます強まる中で、自分たちは生き残れるかどうかへの大きな不安があった。そして准看制度がなくなったら、自分たちの小さな診療所などでは看護婦を確保することができなくなるかもしれないという気持ちが強かったのである。
どんな正論を掲げても医師会のこの危機意識に理解を示すことがなければ、手負いの獅子を追い込むだけのことになってしまう。何かいい切り口が見つからないかと思案を重ねているうちに、これぞ21世紀の診療所と思われる素晴らしい実例にめぐりあうこととなった。
栃木県小山市は町中いたるところに診療所の看板が林立するいわば診療所の激戦区である。そこでひとり気を吐き、大繁盛しているのが「おやま城北クリニック」だった。自治医大病院出身の主任、婦長クラスの実力派看護婦を揃えて展開している訪問看護が人気の秘密だった。 マンションの一室を訪問看護部にして5人の看護婦が一カ月に600人もの患者を診ていた。自宅での療養を支える訪問看護は患者やその家族から大好評で、ビジネスとしても大成功していた。
「大きな病院の中で組織上のさまざまな人間関係に気を使いながら働くよりも、在宅の患者さんを自分から出向いて行って支える訪問看護の方が、自分らしい看護が実践できるように思えるんです」
訪問看護婦たち自身も病院の看護では味わえない手ごたえを感じて、みんないきいきと働いていた。
「日常の生活の中で医療を行なうということは、医療者にとっても病院の中とは全く違った発想が求められてきます。でもそういった医療を求めている人は驚くほどたくさんいるんですね。これほどやりがいを感じる仕事はなかったですね」
理事長の太田秀樹医師はそう語ったが、私は取材しながらこれこそ21世紀型の医療に違いないと実感していた。
少子高齢社会は看護、介護を必要とする人がたくさんいる社会であり、いかに在宅で充実した医療福祉を提供できるかが最大の課題になる。それゆえ地域の医療の担い手である開業医の役割はこれまで以上に大きなものとならざるをえない。あえて言うならば「21世紀は開業医の時代」なのである。
この視点こそ日本医師会の名誉ある撤退に向けて、患者サイドから投げられる最後のカードにちがいないと私は確信した。時代の要請を感じとっている開業医のもとには大卒であろうがベテランであろうが、優秀な看護婦はいくらでも集まるはずである。だから准看制度にこだわらなくても、やる気さえあれば看護婦確保は心配ないというメッセージであった。
現に最近は診療所で働く(正)看護婦が増える傾向にあった。平成4年から一年間に18・5%も増えていた(平成5年厚生省調査)。それは診療所が訪問看護の拠点として改めて注目され始めた証拠だった。
最終的に看護関係者はやるべきことはすべてやった、後は天命を待つのみといった心境だった。そして12月20日、ついに念願の歴史的な全面勝利を手にすることとなったのである。
厚生省では2001年に准看養成停止を実現させるべく早速、準備作業に入った。法律上は保助看法(保健婦助産婦看護婦法)改正案を成立させるという最後のハードルが残っており、今のところは来年の通常国会をメドにしているようである。しかし、せっかく変革に向けての気運が高まったこともあり、法律改正までにあまり時間をかけるべきではないと思う。
さてゴールが見えた今、看護界は過去を清算した上で今後どういう看護婦の未来像を作っていくか、その使命はこれからがむしろ正念場と言えるだろう。
日本の医療界は医師を頂点としたヒエラルキーの体制が未だ根強く残っており、権威主義的体質も変わらない。しかし、私たちは今、医師にできることの限界を知りつつある。医師は決して万能ではない。人間の体の回復において医師による治療というのは一部分を占めているにすぎない。
例えば医師は手術をすれば仕事はほぼ終わったと思うだろうが、患者にとってはその後の方がよほど大変である。手術後のケアの善し悪しによって、社会復帰そのものが大きく左右されてくる。医学の力ではどうしようもない状況に陥った患者をいかに支えるかということは、医師の力を越えた領域である。手術の前であろうが後であろうが、治療が可能であろうがなかろうが、常に患者に寄り添い、患者の目線で支え続けるのが看護婦である。医師は病気を見て、看護婦は人間を見ると言われるが、看護婦が患者をスペシャリストの目で全人格的に見続けるかぎり、これからはむしろ看護婦が医療現場での中心的存在になっていくだろう。
そして看護婦にとっても、改めて「看護とは何か」が厳しく問われてくるにちがいない。アメリカでは看護の質を上げることによって入院日数を減らすことができたというリポートがあるが(メディカル・ナショナル・データバンク調査)、看護の力によって何をどう変えていくのかを、具体的に患者に示していかなければならない。医師のアシスタントではすまされない医療のスペシャリストとしての高い自覚と責任が求められてくるのは当然である。
これから21世紀に向かって、患者中心の医療をどれだけ実現できるかのカギを握っているのが、今度生まれ変わろうとする看護婦である。私は患者の立場からそれを大いに期待しながら、今後の彼女たちの飛躍を見守っていきたいと考えている。