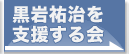
HOME > これまでの著書・コラム > 救急医療について
突然の傷病者を、病院がたらい回しすることだけが、救急医療の問題点なのではない。救急隊員に最低限の医療行為も認められないからこそ、患者は救急車の中で死ぬのだ。
「黒岩さんはずいぶんご熱心に救急医療に取り組んでおられるようですが、今、救急っていうのは何か問題になってるんですかねえ。」去年9月、テレビインタビューを終えた直後の厚生省担当課長のひと言である。厚生省もようやく重い腰を上げ21世紀の救急医療のあり方を考える検討会をスタートさせた。その事についてインタビューした直後のこの言葉に私は愕然とした。厚生省の救急医療に対する認識はその程度なのである。
救急医療の問題と言ってすぐピンとくるのは「病院のたらい回し」である。略和40年代後半から50年代にかけて、救急患者が病院に受け入れを次々と拒否され、それが原因で死亡するケースが続出した。連日マスコミをにぎわせ、日本の救急医療体制は社会問題となった。
確かに今は、そういう意昧では問題にはなっていない。しかし、「社会問題になっていない」という事と、「問題がない」という事とは全く別である。
日本の救急隊は消防署の職員であり、医師法によって医療行為が禁じられているが、先進国の中で、今どき医療のない救急車を走らせているのは日本だけである。そのため、心肺停止からの蘇生率は欧米の4分の1という現状である。すなわち、日本では助かるはずの多くの命が消えているのである。日本の救急医療体制が欧米より10年以上遅れているといわれるのはそこにある。これで「問題がない」と誰が言えるのだろうか。「社会問題化する」に十分な条件はすでに整っているのである。それではどうすれば「社会問題化する」のだろうか。それは埋もれた事実を掘り起こし、現状をより多くの人に知ってもらう事から始めるしかないのではないだろうか。FNN「スーパータイム」では、去年3月から土日の放送を中心に、「救急医療にメス」というシリーズ企画を放送してきた。「日本にも欧米並みに医療行為のできる救急隊を実現しよう」という番組の訴えかけは、視聴者のみなさんからも大きな反響をいただき、テレビニュースとしては異例の1年を超える長期キャンぺ!)ンとなった。毎日毎日あふれかえるニュースを右から左へ伝えていくだけではなく、伝える事を一つの手段として「問題」を「社会問題」にし、さらに行政を動かして形あるものにしたい。
ーーそれが今、私がジャーナリズムにかける夢なのである。
■点滴の針も抜けない救急隊
昭和63年5月、夕刻。
東京都大田区大森の住宅地に、1台の救急車がかけつけた。隊長以下3人の大森救急隊。「老人の急病」という通信室からの指令で現場に急行した彼らであったが、現場に到着するまでは、それ以上の情報は得ていない。現場で傷病者の様子を観察して、それから次の行動を判断することが救急隊の第1の仕事だからである。
佐藤良子さん(仮名)の案内で通された現場は、庭に面した6畳の間。良子さんの母、マサさん(72歳=仮名)は、べッドの上で全身の痙攣を起こしていた。生死の境に立ち会う事は決してめずらしくない救急隊にとって、全身痙攣は見慣れた光景でもある。そのくらいの事で動揺していては、勤まらない。
しかし、この時ばかりは違った。
マサさんの細い腕には、点滴の針がささっていたのである。マサさんは、自宅で点滴中に、全身の痙攣を起こしたのであった。点滴注射はもちろん医師によって行なわれる医療行為である。日本の救急隊員は医師ではないし看護士でもない。彼らは消防署の職員である。彼らは消防の内部研修を受けてはいるものの、そのほとんどは、元消防士か、あるいは今も、火を消すあの消防士なのである。
彼らは、医師法によって医療行為が禁じられている。点滴注射をすることはおろか、その針をぬくことすら、許されていないのである。
「あなたたち、何してるの。早く運んで下さいよ。」
良子さんの絶叫に近い声が飛んだ。マサさんは、目の前で全身をガクガクと震わせている。呼吸も、だんだん荒くなり、吸う息より吐く息しか間こえなくなってきている。まさに一刻一秒を争うギリギリの状況で、すがるような思いで呼んだ救急隊。意外に早く来てくれたなあとホッとしたのもつかの間、自衣を着た大の男3人は、マサさんの傍らで何もしないで呆然としているのである。良子さんの憤りは当然といえよう。
「あの……お医者さんを呼んでいただけませんか。点滴の針を抜いてもらいたいんですが」
隊長の第一声である。
「点滴の針なんかそのままでいいから、とにかく早く運んで下さいよ。」
「私たちは点滴中の患者さんは運べないんです。」
「それなら針をぬけばいいじゃないですか。」
「私たちには点滴の針を抜くことはできないんです。」
全身痙攣の患者のそばで激しく言い争う娘と救急隊。かかりつけの医師は外来診察中ですぐにかけつけることはできず、いたずらに、過ぎてゆく貴重な時間。
良子さんは、その時の様子を次のように語っている。「私は救急隊チーフの人は、せめて看護婦さんくらいの事は、できるのかと思っていました。それなのに、できない、できないの一点張り。大勢いるのに、ただ突っ立っているだけで、時間がもったいなくて……。
結局、もし何かあったら、私が罪をかぶるから、とにかく運んでちょうだいと言って、点滴をしたまま、強引に運んでもらいました。」
佐藤マサさんは、その二カ月後、帰らぬ人となった。「点滴中の患者を運ぶこと自体は、医療行為にあたらない。救急隊に禁じられているわけではない」厚生省健康政策局総務課の見解である。
しかし、現実には、医師の同乗なしに点滴中の患者を搬送することは今の救急隊には荷が重すぎる。佐藤さんの一件から1年たって、東京消防庁は点滴中の患者の搬送の条件整備を行なった。救急業務懇話会の答申を受けて平成元年7月から「救急隊員の救急処置の拡大」ということで実施されたものである。ところがそれですら、救急隊が針をぬいたりさしたりすることを認めたものではない。
点滴のチューブがはずれた時にはつないでもいい、針がぬけた時はそのまま固定して運べーーただそれだけの事である。いかに救急隊員が信用されていないかよくわかる。
救急隊のあり方が質的に変わらない限り、佐藤さんの家で起きたと同様の事は再び起きる可能性は十分にある。
もし点滴中の患者を搬送している途中に、針がぬけたらどうするか。
「早く点滴針をさして下さいよ。」
「いえ、私達はチューブはつなげますが、針はさせません。」
それで家族が納得するだろうか。患者サイドのニーズは、明らかに救急隊員に医療関連資格を求めているのである。
■救急隊は注射器を捨てた
高齢化社会から超高齢化社会へ。昭和63年で65歳以上の老人は全人口の11.2%、1373万人。それが27年後の平成27年には倍の22.5%、数では2.3倍の3064万人にふくれあがることが予想されている(厚生省統計要覧昭和63年版)。
救急車を利用するのは圧倒的に老人が多い。昭和62年のデータを見ても、全国で一年間に救急車を利用した234.8万人のうち、65歳以上の老人は、52万人、22.2%にのぼる。それが、30年後の2020年には、数の上では2.5倍の132万人、救急車を利用する人の42.4%にのぼることが予想されている。まさに救急車の半分は老人が使うことになるのである。さらに救急車を利月する場合を急病、交通事故、一般負傷、その他に分けて見てみると、老人の場合はやはり急病が多い。昭和62年のデータですら、急病全体の30.4%が老人である。30年後には急病の半分以上が老人になる事はまちがいない。
高齢化社会が進むにつれてマサさんのように、自宅で点滴などの医療行為を受ける、いわゆる、”在宅ケア”の患者が増えている。点滴を受ける患者の実数は、厚生省でも把握していないが、自宅で注射をうっている患者は、14万人と推定されている。
来たるべき超高齢化社会にむけて、厚生省はこの在宅ケアを積極的に推進する方針を打ち出している。老人の長期療養患者をどんどん病院に収容していけば、病院のベッドはどこも老人でいっぱいになり、新規入院患者は全く受け付けられなくなるだろう。
自宅での療養生活、在宅ケアは、超高齢化社会の医療体制を守るうえで、不可欠のものである。老人の立場から言っても、入院するより在宅のまま医療を受けられるならそれにこしたことはない。家族に囲まれて、家族の手料理を食べて治療に専念できるなら、誰しもその方がいいと思うだろう。
ところが、このようにかなり高度の医療、そして医療機器が、一般の住宅に入りこんでくると、それだけ緊急時の対応がむつかしくなるのは、これまで見てきた事例でも明らかである。
もちろん、点滴注射にしても、医師が住診して注射針をさしたり抜いたりする。在宅ケアは医師の目の屈く所で、というのが基本である。
しかし、点滴をしている間中、医師がいつもいつも付き添っているわけにはいかない。佐藤マサさんのように、点滴をしている最中に、突然の異変が生じ、しかもそこに医師がかけつけられない状況というのは、日常的に起こりうる事なのである。
そんな時、どうするか。
当然のように119番。救急車を呼ぶことになる。5分もたたないうちに近くの消防署から白衣を者た救急隊がやってくるだろう。白衣は着ているが、医者でも看護士でもない、医療行為を禁じられた消防署員。その救急隊が、突然、医療の現場に呼び出され、医療行為を求められる。
「我々は医療行為はできません」と正直に言えば家族から、「なんでそれくらいの事、できないんだ」と怒鳴られる。
救急隊も家族もつらい。でも一番つらいのは、生命の危機にさらされながら、助けてもらえない患者本人なのではないだろうか。
しかし、驚くべきことに、日本の救急隊も30年前は注射をうっていた。消防庁救急救助課資器材担当の馬場主任は、懐しそうにこう語ってくれた。
「当時の注射はメタカンファーというカンフル注射でした。私も1度使ったことがあります。昭和30年頃の事ですが交通事故で車と車にはさまれた傷病者が、あまり痛がるもので、カンフル注射をしましょうかと聞いたところ、ぜひそうしてくれというのでうちました。」
かつて注射をうっていた救急隊。実はある一つの出来事が契機となり、救急隊は注射器を捨てる連命をたどったのである。昭和32年10月4日、午後8時40分頃、国電有楽町駅長室に酒に酔った男が入り、ドアのガラスを破ったり、乱暴を働いた。このため丸の内警察署では、この27歳の会社員を器物損壊の現行犯で逮捕、留置した。ところがこの男は、5日午前零時頃、署内で急に元気がなくなったため、警察は救急車を要静。かけつけた丸の内救急隊がこの男を近くの日比谷病院に搬送したがまもなく死亡したのである。丸の内警察署では、「アルコール中毒による心臓マヒということで処理していたが、遺族は「警察署内で警官に暴行を加えられたのではないか」と疑いをもち、告訴。東京地検特捜部が捜査を始めることになった。
本事件の問題はあくまで”警察官の暴行の有無”にあり、救急隊の処置は事件とは無関係であった。ところが、地検の捜査の過程で、救急隊の処置についても調べが行なわれ、カンフル注射をしていた事実が明らかになった。
その時の救急隊員、後藤松治さんは次のように証言している。「私たちが現場に着いた時、患者はすでに仮死状態でした。仮死状態の患者に対してはまずカンフル注射、それから人工呼吸というように指示されていましたので、隊長の命令に従いカンフル注射を行ないました。結局患者は死亡したわけですが、私たちにはカンフル注射と死に因果関係があったかどうかわかりません。でも、それからあとで、注射器を回収することになったのを覚えています。」仮死状態の患者には、まずカンフル注射。それが当時の救急隊の現場処置であった。今はれっきとした医療行為とされ、救急隊には禁じられている注射。それが当時は、あたり前の事として行なわれていたのである。ところが、ひとたび地検の調べの俎上にのぼった注射について、事件とは無関係である事が確認されたにも関わらず、次のような注意勧告が検事から東京消防庁に対して、行なわれたのである。「救急隊員の行なう注射は、法的根拠が明確でなく、厳正な解釈では医師法に抵触するものと解されるので、今後問題を惹起しない前に中止してはどうか。」この勧告は法的になんら制約を与えるものではないが、東京消防庁は、いたずらに物議をかもすよりは、はっきり結論の出るまではカンフル注射を行なわない方が得策と判断し、昭和33年1月27日、部長指示により全部の救急隊から注射器と注射液を一時的に引きあげたのである。
この事が報道されると、世論の反響は大きく「いわゆる”社会問題化”し、都議会からさらには国会まで論議が発展、衆議院の社会労働委員会で取り上げられるに至ったのである。
<昭和33年3月12日衆議院社会労働委員会における厚生省当局との間答の要旨
問)
救急隊に乗りこんでいる救急隊員が災害によって負傷し、または疾病にかかった者を最寄りの指定病院等に輸送するにあたって、患者の病状が重篤で生命に危険ありと認定した際に、カンフル皮下注射等の救急処置を行なうのは医師法違反であるか?
答 当該負傷者等の生命、身体に対する現在の危険を避けるためにやむを得ないと認められる事情の下に行なうものである限りは、一般的には医師法第17条にいう医業を行なうものとは解されない。従ってこのような場合には医師法違反にならないと考える。
理由)
医師法第17条にいう「医業」とは医行為を業とすることをいうのであるが、この場合の業とは、反覆継続する意思をもって医行為を行なうことを、意味するものと解釈すべきである。ところが救急車のように緊急状態の場合における業務は社会通念上反覆継続して行なう意思をもって行われたとは認められない。
従って本件のような緊急状態における「カンフル注射」等の救急処置は個々の行為自体を単独にみれば医行為である場合があるとしても、全体的にみれば医師法でいう医業に該当するものとは考えられない。(以下略)>
つまり衆議員社会労働委員会の厚生省答弁は、負傷者等の生命、身体が危機にさらされている場合の救急隊の注射は医師法違反にあたらないと明言しているのである。
このため東京消防庁はひとたび引きあげた注射器を2月中句に再び配置し、慎重に使用することとなった。その年の6月には、全国の都市府県知事あてに厚生省医務局長名の通達が出されているが、ここでも、やむを得ない場合の注射は医師法違反にあたらないと明確に記されているのである。
<医発第480号の1
昭和33年6月9日 厚生省医務局長
各都市府県知事殿
消防職員が患者に対して行なう救急処置について
先般、東京都下において、消防関係救急業務に従事する消防職員が、患者を病院に輸送するに際してカンフル皮下注射を行ない、ために患者の病状を悪変させたのではないかと疑われる事件が発生したが、医師法第17条の規定と、これら消防職員の行なう救急処置との関係については、左記のとおり解されるので、関係方面に周知徹底のうえ、人命の保護に遺憾のないようにされたい。
1、消防関係救急業務として患者を指定病院等に輸送するに際して患者に救急処置を施す必要が生じた場合は、原則として医師がこれを行なうものであること。
2、しかしながら右のような場合に一般の消防職員が、当該患者の生命身体に対する現在の危難をさけるために、やむを得ないと認められる事情の下にカンフル皮下注射等を行うことは、一般的には反覆継続の意思をもってするものとは考えられず、従って医師法第17条にいう医業を行うものとは解されないこと>(傍点筆者)
■医師法の解釈が変わった
このようにして再配備された注射器ではあったが、その後救急隊員が実際に注射をうつ件数はかなり減少していったようだ。医師法違反にはあたらなかったとはいえ、一歩間違えると医師法違反に間われるかもしれないという恐怖感が救急隊から積極的な行為を奪っていったにちがいない。
結局、昭和41年42年頃に最終的に全救急車から注射器は回収されることになった。その時も、ある消防署長が弁護士に仮定の話として「もし救急隊の注射が原因で死亡したとしたらどうなるか。」と相談したところ、「医師法違反に間われる危険性は高い。」という答えをもらった。それによって注射器回収にふみきったというのである。つまり、救急隊の注射は一度も医師法違反として摘発されたことも糾弾されたこともないまま、消え去ったのである。
厚生省健康政策局医事課の丸山課長は、はっきりと述べている。「救急隊が注射をすることは医師法違反にあたる。たとえ1回限りという事で行なおうと、緊急避難という状況であろうと、救急隊である限り反覆継続する行為と見なされることは避けられない。」いつの間にか医師法の解釈は変わってしまっている。昭和33年6月の厚生省医務局長の見解とは明らかに異なっているのがわかる。「注射一本うてない救急隊」それは消防庁自らがかつて選択した姿だったのである。
■病院外で医療は存在しない
平成元年3月。東京の御徒町駅のプラットホームで、群馬から上京中の男性が突然卒倒。15時53分駅員が119番通報。7分後上野救急隊がかけつけた時には、すでに心臓停止。救急隊は早速、心臓マッサージと人工呼吸を行ないながら、日本医科大救命救急センターに搬送した。
日本医科大に到着したのは、16時19分。処置室のベッドで待ちうけていた七人の救急医に引き波すその瞬間まで、救急隊は汗びっしょりになりながら心臓マッサージを続けた。
消防庁の通信指令室からのホットラインで、すでに用意万端整った救命救急センター。救急隊から患者を受けとるやいなや、7人の医師がいっせいに群がるように処置を開始する。衣服は大きなハサミで一瞬のうちに切り裂かれ、むしりとられるようにして、患者は全裸になる。心臓マッサージは医師によって続けられるが、同時に静脈確保、輸液、気管に管を通して効率的な人工呼吸を行なうための気管内挿管が行われる。心電図には大きく乱れながらも波形が表われ、この患者がまだ死んでいないことを実感させる。心拍が100台から70台、30台、と急激に下がり一瞬ゼロに・・・しかし、また回復。除細動器が胸にあてられ、、電気ショック。体全体がベッドから浮きあがる程の衝撃。ドクターの目がいっせいに心電図にむけられるが、大きく乱れたまま。自発的な心臓の動きは戻らない。心臓マッサージ再開。患者の腹は大きくふくらんでいる。これは、救急隊の人工呼吸によるもの。再び電気ショック。脈は戻らない。心臓マッサージの手を離してみる。しばらくは、腹が大きく波うっている。深呼吸をしているように。しかし、脈は戻らない。心電図の波形の乱れは一層激しくなってくる。
心臓マッサージ。電気ショック。そのくり返しだが、ドクターの表情にも徐々に絶望感が漂い始めてくる。病院到着40分後、心臓マッサージが終わる。瞳孔を確認するドクター、静かに時計を見上げ「5時」とひとこと。全員がベッドのまわりを取り囲み一礼。死の確定。
この患者の場合、心臓停止から救急隊の心臓マッサージまで、少なくとも10分近く経過している。そして、本格的な医療行為まで、さらに20分経っている。これで助かるなら、本当に奇跡である。
ワシントン大学のリチャード・O・カミンズ教授の論文によると、心臓マッサージ、人工呼吸だけの蘇生と、心臓マッサージ、人工呼吸、さらに、除細動(電気ショック)、点滴などの投薬を含めた蘇生とでは、蘇生率に3.5倍の開きがある。
この差は、ちょうどアメリカと日本の救急隊の蘇生率の差にあたる。5分後に救急車が現場に到着するのは同じとしても、心臓マッサージと人工呼吸しか許されない日本の救急隊と、医療行為の許されたアメリカの救急隊とでは、こんなに大きな差があるのである。
20分以上たって救命の医療行為を始めても、間に合わない。救命救急センターに、どれだけ優秀なスタッフがそろっていても、どれだけ最新鋭の設備が整っていても、時間の壁は決して乗り越えることができない。救命救急センターは、文字通り生死の境をさまようような重篤の患者のみが送られてくる。
今の救急隊の運びこんでくる心肺停止の患者の多くは、間に合わない。救命救急センターのドクターから、「もう心肺停止の患者は連れてこないで欲しい」という声まで、あがっているそうだ。
蘇生、その感動を期待しない人はいない。しかし、助かるはずの多くの命が救えないーーそれが日本の救急医療体制なのだ。
プレホスピタルケア、すなわち病院到着前の医療が最近特に、救急医学会の中でも注目を集めてきた。日本は病院の中には世界の最高水準の医療が存在するが、病院の外には医療そのものが存在しないといっても過言ではない。救命救急は時間との戦いである。心臓停止から5分以内に救命の医療行為が行なえれば50%の命は助かる。どんなに救急車が早く走ろうとも5分以内に、病院に収容するのは不可能だろう。人の命を助けるためには、病院到着前の医療がなんとしても必要なのである。
日本のプレホスピタルケアは空白である。しかし、先進国と呼ばれる国の中で医療のない救急車を走らせているのは今や日本だけである。日本の恥と言ってもいいだろう。ところでそのプレホスピタルケアには2つの方法がある。ひとつはパラメディック(救急看護士)救急隊に限定された救命の医療行為の資格を求めるもので、アメリカ、イギリス、カナダ等で採用されている。もうひとつはドクターカー(医師同乗救急車)医師が救急車に乗って現場に行くシステムで、フランス、西ドイツ等で採用されている。日本がプレホスピタルケアを実現するためには、パラメディック、ドクターカーのいずれを選ぶべきなのか。私は、アメリカとフランスに飛んで、救急医療の現状を取材した。
アメリカにおけるパラメディックの歴史をふり返る時に、私たちが忘れてはならない出来事がある。それは、あのベトナム戦争である。
1966年、ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンスが出したレポートには、「生命にかかわる負傷をした場合、助かる確率は市街地よりも戦場の方が高い」と記されている。当時、街の中は葬儀屋の救急車しかなかったが、それよりも、衛生兵がへリコプターでいつでも飛んでくる戦場の方が人の命は助かるというのである。皮肉な話ではあるが、それほど当時のアメリカの救急体制は遅れていたのである。
戦場で負傷した兵士の死亡率は、第一次大戦当時は8%であったが、このベトナム戦争時は2%にまで下がったというデータもある。衛生兵の活躍ぶりはこのデータからも裏付けられている。
しかし、衛生兵の医療行為はいくら戦場であるからといっても、彼らの独断で行なっていたのではない。基本的には、軍医と無線交信をしながら、すなわち医師の監督下において行なっていたのである。「無線交信による医療行為」ーーこれが衛生兵とパラメディックをつなぐ最大のポィントである。アメリカにおいても、医療行為が医師にのみ許された特別な行為であることは変わりない。ただ、アメリカの場合は、医師が医療行為を独占するのではなく、ある一定の条件のもとに、能力を持つ人たちと分担しようという発想がある。ここが日本と最もちがうところである。
パラメディックは必ず救急病院と無線連絡をとりながら医師の監督下において現場で治療を行なっている。救急現場で必要な医療行為というのは限られている。現場で頭や胸を開いたりする大手術など行なうことはない。腎臓病や肝臓病をその場ですぐ治すなどということはありえない。あくまで当面さし迫っている生命の危機を脱することが重要なのである。
したがってパラメディックに必要とされる行為も自ずから限定されてくる。輸液路の確保、輸液や代用血漿剤の投与、胃チューブによる胃吸引、気管内挿管、検査用の血液採取、心電図の解読、助細動、薬品の静脈注射ならびに経ロ、局所投与等である。この限られた医療行為の技術を彼らは徹底した教育訓練により身につけているのである。
最初の400時間、教室で講義と実技研修を受けた後、最低172時間の病院内実習が行なわれる。ハーパーUCLAメディカルセンターの救急部など提携先の病院で、実際の救急患者を相手に観察力や判断力を養うことになる。その次は480時間、現役のパラメディックに密着し、救急現場での実習を行なう。ここで24時間の当番勤務を20日間経験することになる。このように1000時間、およそ半年の全過程を修了してはじめてEMT・Pの受験資格が得られるのである。
8人ずつで1つのグループを作り、研修を進めていくが、そのつど試験があり主要5教科のうち1つでも75点以下の成績をとると、本科から仮本科に落とされる。そこで再び落第点をとると退学させられてしまう。受講者の15%は途中で落伍してしまうということだ。しかもこのパラメディックの資格は、2年ごとに再試験を受け更新しなければならない。このような厳しい教育・試験制度によりパラメディックの質が保たれているのである。
私自身が、ロス市内で取材した中からきわめて印象的だったシーンを紹介しよう。
案内してくれたパラメディック指令官は、あのベトナム衛生兵出身のD・トンプソン氏である。彼がパラメディック出動無線の中から選択し、急行してくれた現場は、中流の黒人家庭であった。老婦人が自宅で心臓発作を起こしたという。私達が到着した時はすでにパラメディックが着いており、自宅内で治療をしている最中であった。私達の取材に関しては、トンプソン氏が現場で了解を得てくれる事になっていたため、私達はしばらく車の中で様子を窺っていた。トンプソン氏は、部屋の中をちょっと覗いただけで戻ってきて、救急車の所で撮影するように言った。部屋の中が狭くて撮影するスペースがないし、まもなく処置が終わり運び出すことになるからということであった。
私達はその通り、救急車の所でカメラを構えて待っていた。トンプソン氏のことば通り患者が運び出されるのにそれほど時間はかからなかった。ストレッチャー上の老婦人は、鼻にチューブが通され、点滴が施されていた。意識はしっかりしているようだが、ギョロッとした大きな眼にはカがなかった。私達を見ても何の反応も示さなかった。一応容態は落ち着いているように見えた。玄関から救急車まで20メートルくらいあったが、ちょうどカメラに向かってまっすぐ進んでくるような形になった。娘らしき女性が泣きながらつき添っていた。彼女も私達には気づかない様子だった。
ところが、患者を救急車に移し替えてしばらくしてである。パラメディックが救急車の中で聴診器をあてたり、点滴を固定したりしている様子を撮影していた時である。娘がそこで初めて私達に気づいたかのように、かなり鋭い口調で迫ってきた。
「あんたたち、何の真似?何やってんのよォーッ」
自分の母親が生きるか死ぬかという時に、カメラを回されて怒らない方がおかしい。ただその時、私達はトンプソン氏がすでに了解を得てくれているものとばかり思っていたのである。「何やってんのよォーッ」ほぼ絶叫に近いその声を聞いて、トンプソン氏がかけつけてくれた。そして彼女に、きわめて冷静に事情を説明し、これはパラメディックを日本に紹介するための番組だから取材に協力して欲しいと頭を下げてくれた。
するとどうだろう。娘の態度は一変した。
「そういう事情があったなんて知らずに、興奮してしまってごめんなさいね。」彼女に素直にあやまられた私たちの方が驚いてしまったが、パラメディックの社会的信用度を垣間見たような気がした。
パラメディック(EMT・P)の教育過程はカリフォルニア州法に定められた基準に沿って作られたもので、トータル1000時間を超える。内容は、講義、臨床、現場活動実習と分かれており、実技や実習も重視している点が特徴的である。
■フランスのドクターカー
フランスのドクターカーシステムはサミュと呼ばれる。今やフランス全土をカバーする救急医療の最前線の基地であるが、私はパリのサミュ本部を取材することとなった。
サミュは医療機関ではあるが、病院ではない。医師はいるがベッドも処置室も手術室もない。救急出動を専門とする医師の待機所なのである。医師は病院にいて患者の来るのを待っているものだ、という我々日本人の常識からすると、奇異にさえ感じられる。
サミュ本部に手術室はないが、救急車自体がモービルICUと呼ばれ手術室並みの機能を備えている。救急医療は時間との戦いーーそれをつきつめるとまさにこうなる。病院で待つより現場に出て行く。緊急の場合には医師が病院ごと現場にかけつけ、その場で最善の治療を始めるのである。サミュが市民の絶大な信頼を勝ちえているというのもうなずける。
サミュはボランティア団体でも、民間の企業グループでもない。歴としたフランス厚生省主管の国家組織なのである。電話番号は15番。このダイヤルさえ回せばフランスのどこにいてもサミュにつながり、医師を呼ぶことができる。
サミュのスタッフは医師だけではない。看護士やインターンの医学生もいる。救急車の運転を担当するのは消防士で消防本部から派遣されている。
消防土には運転しかさせない。ここにサミュの基本的姿勢がよく現われている。救急はあくまで、医療の現場、なのである。それは病院と同じである。だからその主役は医師であり、補助スタッフは看護士である。消防士は医療行為とは明確に一線を画されているのである。
ただし、救急車の運用に関しては消防の機動カが生かされている。短時間で的確に目的地まで緊急車両を走らせる消防士のドライブテクニックが、サミュの機動力を支えているのである。
パリのサミュ本部にある救急車は全部で11台。大きく分けて第一種と第二種に分かれている。第一種は医療設備の整った車で、一般用6台、小児用2台。第二種は日本の救急車並みで特に医療設備はなく、傷病者を搬送するための車で、これが3台ある。
サミュの救急車でも医師の乗らない場合がある。誤解してはいけないのは、フランスのすべての救急車に医師が乗っているわけではない。フランス人でも、指を少し切ったとか、腹が少し痛むといった程度の事で救急車を呼ぶことはある。そんな時、いちいち医師がかけつけていては、いくら医師がいても足りないだろう。
ここにサミュを支えるもう一つの重要な機能が浮かびあがってくる。すなわち、電話による患者の重症度判断である。それは電話医療相談の側面も持ち合わせている。
専門的にトレーニングされた交換手がまず電話に出て、必要があれば医師と代わる。医師は、電話で相手の症状を聞き、重症、中症、軽症を判断する。この判断でその後のすべての対応が決まるだけに、電話を受ける医師には十分な経験と能力が求められている。医師が軽症と判断した場合は、電話でアドバイスをするだけの事もある。この時は救急車は出動しない。中症、重症で緊急性を要すると判断した場合に限り、サミュのモービルICUと呼ばれる医療救急車を出動させる。もちろん医師が乗っていく。救急要請を選別し、効率的に、医師を救急車に乗せることが、サミュの質を守る大きなポイントとなっているのである。
アメリカのパラメディックについても詳しい、パリサミュ本部の責任者のパリエ教技に聞いてみた。日本はパラメディック、ドクターカー、いずれを選ぶのがいいと思うかと。
当然、「ドクターカー」という答えが返ってくると思っていたが、意外に彼女はこのように答えた。
「要するにお金の問題です。救急医療にたくさんお金をかけられるならサミュのようなドクターカーがいいでしょう。ドクターが救急車に乗るわけですからどうしてもお金はかかりますよ。もし、そんなにお金がないならパラメディックがいいでしょう。パラメディックの方が安くつくのはまちがいないでしょう。」
■サミュかパラメディックか
パラメディックかドクターカーか。私は今次のように考えている。
ドクターカーというのは、今でもやろうと思えばできる。医師自身が救急車に乗って現場に行こうというその気持ちさえあればできる。現に兵庫県西宮市や福島市などいくつかの消防本部では実施している。もっとも、今、日本にあるドクターカーは、フランスのサミュとは比べものにならない貧弱なものである。
ところが、パラメディックというのは、医師法第17条との関連をどうするか明確にしない限りできない。すなわち、パラメディックは医師でない人間に医療行為の一部を認めようとするものだからである。 今の日本の現状は、ようやくプレホスピタルケアに目が向けられてきたばかりであり、まだまだ議論が十分に行なわれているとはいえない。日本全体としては、救急車の数や救急病院の数といった救急医療体制の量的な整備がやっと一段落した。これからはそろそろ質的な充実をめざそうかという程度の段階なのである。
そのため、いずれも態度を明確に打ち出してはいない。厚生省も自治省も、それぞれ検討委員会を設け、検討している最中である。
しかし、パラメディックに対する日本医師会の反対がきわめて強いことだけははっきりしている。医師以外の人間に医療行為を認めるとはとんでもない、危険きわまりない--というのが、日本医師会の基本的な考え方である。医師法を楯にしたパラメディック潰しは、この議論が表面化すればする程、激しいものとなってきている。
日本医師会の態度がはっきりしているから厚生省の取ろうとしている道も自ずから見えてくる。めざすものは、「パラメディック潰し」である。その代替案としてドクターカー制度を提唱はしているが、フランスのサミュのような徹底したドクターカーシステムをめざしているとはとても思えない。せいぜい西宮市などで実施しているランデブー方式といわれるドクターカー--すなわち救急車が病院に医師を迎えに行き、現場まで連れていく制度でお茶をにごそうとしているとしか思えない。
救急車に乗る事を専門にした医師が24時間出動態勢を取るサミュと、このようなドクターカーとは質的に全く異なるものなのである。ドクターカーということばに惑わされてはいけない。現に、西宮消防局で10年以上実施してきたこのドクターカーについて、消防側も病院側もそろって、限界を主張し、パラメディックの必要性を主張しているのである。どんなにがんばっても、医師が現場に行くには時間がかかる。救急隊が二次救命処置まで行なわないと、現実には間に合わないというのである。
同じ医師でも、実際に救命救急センターで働いている医師のほとんどは、パラメディックを主張する。気管内挿管、除細動、点滴の二次救命処置は、徹底した訓練によって救急隊員にマスターさせることは可能だと言うのである。ある救急ドクターは次のように語った。「医者なら救急ができると思ったら大まちがい。内科の開業医の先生なんか、血だらけの患者を見たら、どうしていいかわからず呆然としていますよ。現場に慣れた救急隊員の方が、よっぽど冷静だし役に立ちますよ。医師会の先生は開業医中心だから、救急現場の事は知らないでしょう。ドクターカーなんて言っても、自分は救急車に乗らないことを前提にしているんだから、話になりませんよ。」
私は、決してドクターカーを否定しようとは思わない。どんな形にせよドクターカー導入の動きには大賛成である。医師が現場に来てくれるというのに反対する理由はどこにもない。しかしそれと同時に、パラメディックにも賛成なのである。日本にも、パラメディック、救急看護士の資格制度を導入すべきであると考える。
私は医師法を改正しないでもパラメディック導入は可能であると考えている。看護婦に注射を認めている保助看法のような法律で--例えば救急看護士法--パラメディックの業務を規定すればいい。そのかわり、一年程度の研修と厳格な国家試験は必要であろう。それは、まさにアメリカのパラメディックそのものである。
ドクターカーを強く主張し、パラメディックには絶対反対という、ある高名な麻酔科の医師が私にこう言った。
「せっかく医師が病院の外に出ていこうとしているんですよ。パラメディックによって、せっかくのその茅をつぶさないで下さいよ。」
私はくり返し主張するが、決してドクターカーの芽をつぶそうなどとは考えていない。ただドクターカーとパラメディックは共存しうるものと考えているのである。
ドクターが病院の外に出ていこうとするその芽はつぶさない。それと同じように、消防の救急隊員もなんとかして人の命を救いたい、自分たちも真剣に勉強して二次救命処置まで身につけたいと本気で考え始めている、その芽もつぶさないで欲しいのである。私は日本医師会が主導する「パラメディック潰し」の動きに対して、あくまで反対していきたいと考えているのである。