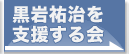
HOME > これまでの著書・コラム > 救急医療について
心肺蘇生をめぐって
救急救命士誕生の背景と今後の課題
^Inside The Emergency Medicine, Paramedics promotion campaign and its outside.
黒岩 祐治 フジテレビジョン
救急救命士の発足は時代の要請であったが,世論の支持とはすなわち,マスコミの後押しの力であったと言うこともできる。
今回は,プレホスピタルケアの問題に早くよりかかわり,平成元年3月から救急救命士法が成立した平成3年4月まで,計80回にわたって「救急医療にメス」のシリーズキャンペーンを続けたフジテレビの黒岩キャスターに,‘救急救命士誕生'について,ジャーナリストという立場を明確にして語っていただいた。
医師ら医療従事者に,異なる意見があるとしても当然である。しかし,医療を受ける側の市民が医療について発言することは,今後ますますあるべき方向であろう。
(須崎 紳一郎:コラムも)
■救急医学と救急医療のあいだで
先日,ある大学の主催する「救急医学と救急医療」と題した鼎談に参加させていただいたが,私が興味を引かれたのはそのタイトルだった。わざわざ医学と医療を区別して表題にしたところに,主催者の鮮明な問題意識が浮き彫りになっているように思えた。
医学教育を受けたこともない私にとって,救急医学の議論に参加することは望むべくもない。こういう症状にはこういう処置がいいとか,この薬をこんな風に使えばこんな効果が期待できるとか,そんな医学上の議論は,門外漢の私には,専門家のみなさんにお任せするしかない。
しかし,救急医療となれば話は別である。医学が病気やけがそのものを対象としているのに対して,医療とはその病気やけがを背負った人間を相手にしている。学問としての医学を生身の人間に実践するのが医療である。医学はいわゆる純粋科学であるが,医療はそこに社会学的要素が加わってくる。
特に救急医療の場合は,この社会学的要素が大きく膨らんでいると考えるべきであろう。救急医学のレベルがどんなに高くても,病院に到着してからすべての処置が始まるのでは,大きな成果を期待することは不可能である。患者が発生した現場から病院まで,どのようにして切れ目のない医療を実現していくのか,それが目に見える成果を上げるために絶対的に必要な条件である。
医師は病院の中でこそすべての医療従事者の頂点に立つ絶対的なリーダーではあるが,病院を一歩外に出れば,そこは彼らの論理と権限の及ぶ世界ではない。救急車は消防署の管轄であり,救急車が到着するまでを支えているのは日常生活を営む普通の市民である。このように,病院の枠をはみ出したトータルな発想が求められているのが救急医療の世界であり,それだからこそ,われわれ部外者も医師と同じ土俵に立って議論することができるのである。
■キャンペーンと世論の圧力
平成元年から2年間,私はFNNスーパータイムでプレホスピタルケア(病院到着前医療)の充実に絞った救急医療キャンペーンを展開した。当初は,10年かかっても無理だろうといわれた闘いであったが,行政も国会も動き始めて,ついに平成3年,念願の救急救命士制度が誕生した。
心肺停止状態から一刻も早く救命処置を始めなければ蘇生率の向上は望めないという医学上の結論を,どのようにして救急医療体制という社会的システムとして実現するか,それが私のキャンペーンの目標であった。
「日本にもアメリカの救急隊,パラメディックのような医療行為のできる救急隊を実現しよう」という主張を掲げたとき,私はまさか反対する人がいるとは思わなかった。しかし現実には,「パラメディックなど議論にも値しない」という強硬反対論の洗礼を受けることになった。その急先鋒は日本医師会と麻酔学会であった。
彼らがパラメディックに反対する最大の根拠は医師法であった。パラメディックは,「医師でなければ医業をなしてはならない」という,医師法第17条の規定に違反しているというのである。医療行為といっても,救命の3点セットと呼ばれた「点滴」,「除細動」,「気管内挿管」に限ったことなのだが,医師でない救急隊がそういう処置を始めると,医療現場は大混乱して医療そのものへの信頼性が失われる,というのであった。
しかし,救命救急センターの医師の多くはパラメディック賛成派であった。「救命救急の現場では,医師法がどうのこうのと言っている状況ではない。緊急避難という考え方で,とにかく命を救うということを第一にすべきである」と主張していた。私自身,こちらの主張のほうが正しいと感じていたからこそ,このキャンペーンを始めたのであるが,視聴者の反応も圧倒的にパラメディック支持だった。
結局,この論争はパラメディック支持派の大勝利に終わり,日本版パラメディックともいうべき救急救命士制度誕生に結び付いたのである。私はその最大の要因は世論の盛り上がりにあったと思っている。医師法に固執し,新しい制度導入に反対を続ける日本医師会の主張に,共感の輪は広がらなかった。世論の後押しがあったからこそ,行政も国会もその波をうまく利用することができたのである。
専門家のあいだであれほど激しい意見の対立があったものが,国会においてはほとんど議論もないまま,自民党から共産党まで全会一致で成立したその経緯をみても,いかに世論の圧力が大きかったかがよくわかる。
■“やらせ報道”疑惑!?
世論形成の作業に,私もテレビジャーナリズムの立場から参加できたと思っているが,意見の対立が存在している問題に対して,その一方を後押しするキャンペーンをテレビで展開することの是非については,問題視する声がなかったわけではない。しかし,私は反論についてはいつでもその機会を提供する姿勢を明確にしてきた。それが,思い切った提言を行いながら,ジャーナリズムの公正さを確保するための私なりの方法論であった。
最終的に問題はいっさい起きなかったが,一部から恨みをかっていたことだけは間違いなかったようだ。キャンペーンが終わったあと,私はあるマイナー新聞に中傷記事を掲載されたのである。
「やらせ報道だった!? パラメディック推進役のフジテレビ黒岩キャスターのキャンペーン」
ご丁寧にも私の顔写真入りで,刺激的な「やらせ報道」という大きな活字が踊っていた。私自身になんの取材もなかっただけに全くの寝耳に水であった。何をもってやらせというのか,思い当たる節は全然なかったが,私は記事を読んで初めてその背景がわかった。誰がその情報の発信元であり,どうしてその人が私のことをそんな風に新聞社に売り込んだのか,すべてがその記事から読み取ることができた。
それは,ある麻酔ドクターの仕業だった。消防の機関誌に寄せた私の一文を悪意で解釈して,記者に書かせたもののようであった。
その一文とは,キャンペーンの初期に,救急隊長への実務研修を取材したときのエピソードをまとめたものであった。その当時は消防内部でもようやくパラメディックについての議論が始まったばかりであったが,取材したときの研修では,救急隊長に気管内挿管の実習が行われていた。いま議論の対象になっている気管内挿管がどんなものなのかを一応体験してもらおうという狙いで行われたものであった。
気管内挿管という行為は,素人目にはかなり恐ろしげに見えるものである。救急隊長たちは練習用の人形相手にみんな一生懸命取り組んでいるのだが,なかなかうまくいかない。もちろん彼らにとっては生まれて初めてのことであり,最初からうまくいくはずなどないことはわかっているのだが,彼らの実技の様子を見ているうちに私もだんだん不安になってきた。彼らの危うげな行為が映像になって映し出されると,その印象が救急隊全体のイメージになってしまうことは間違いない。この映像だけで,パラメディックを求める声そのものがあっという間に消えてなくなってしまうことだってあるかもしれない。頼りの編集マンもこの映像を見て,「この人たちにこんなことされるくらいなら,僕だったら死んだほうがましだ」などと言いだす始末であった。
しかし,私たちが論じようとしているのは今現在の救急隊ではなく,未来の救急隊である。未来に向けて医療行為のできる救急隊の可能性を論じようとしているときに,初めて取り組む救急隊長たちの不体裁な練習の映像が予見を与えてしまうことは何としても避けなければならない。そのために,私は比較的うまくできている人の映像を中心に編集し,できるだけボロが出ないように心掛けた。
私はそのときの苦悩を正直に機関誌に書いたのであるが,これを「やらせ報道」と決めつけられたのであった。
私たちはジャーナリストとして事実を伝えなければならない使命を担っているが,映像に写っているものをそのまま編集したらそれで事実が伝わるかといえばそうではない。同じ取材映像でも,編集によって全く別の意味をもったものに仕上がる。取材者として何を訴えたいかで,編集の仕方も変わってくるのである。しかも未来を語るときには,今ある映像を使うことにおのずと制約がかかってくるのはやむを得ないことなのである。
ジャーナリストとしては命取りにもなりかねない「やらせ報道」の汚名ではあったが,結局,その後何の反響もないままに終わった。私自身はやり切れない思いだったが,冷静になって考えてみれば,この麻酔ドクターの私に対する誹謗中傷などは,実は取るに足りない問題だった。それより問題なのは,彼が根本的に抱いているに違いない,救急隊への不信感のほうであった。これが救急救命士の未来に暗い影を落とすことになりはしないかと不安であった。
■救急救命士はパラメディックになれるか?
第一期の救急救命士が誕生してから4年たった。東京消防庁ではすべての救急車に24時間態勢で救急救命士が同乗するようになり,もはやこの制度に反対する人はいない。そして,今度は改めて救急救命士の応急処置の範囲をさらに拡大すべきという議論が起きようとしている。
救急救命士はアメリカのパラメディックを真似た資格であったが,法案作成の過程で強硬反対派に配慮して妥協が行われ,パラメディックに比べていくつかの点で処置範囲が限られている。救命の3点セットの中で,特に麻酔ドクターの反対の強かった「気管内挿管」が器具を使った「気道確保」に格下げされ,パラメディックが使用している「点滴」での薬品もほとんど認められなかった。しかも,医師の指示の下での処置という点が厳密に規定された。
そろそろこれをパラメディック並みに処置範囲を拡大しようということなのである。本来は,初めからパラメディック並みにするべきだったのだが,反対派のメンツを立てるためにやむをえず行われた妥協であった。当時の救急隊は,ドクターからそれだけの信頼感は得ていなかった。いつになったらグレードアップできるかどうかということは,救急救命士たちの活躍ぶりにかかっていた。
さて,今の時点でそのような環境整備ができたといえるかどうかなのだが,残念ながら私には,もう大丈夫と言いきるだけの自信はない。
私がかつて取材したアメリカのパラメディックは,ドクターら医療スタッフと日頃から顔の見えるつきあいをしていた。そこで生まれる信頼感が緊急時の連携プレーにつながっているようであった。果たして救急救命士はドクターたちとそういう関係を築き上げているだろうか。あの麻酔ドクターの不信感を解消させるような,新たな人間関係を作れているだろうか。
また,パラメディックは市民から絶大な信頼感を得ていた。パラメディックが来てくれるというだけで安心感が広がり,市民たちは現場では驚くほど彼らの指示に忠実に従うのであった。それは日頃からあらゆるメディアを通じて,彼らの活躍ぶりが紹介されていたこととも大いに関係があるということであった。
果たして,救急救命士は一般市民の信頼感を十分に得ているといえるだろうか。そもそも今の救急救命士が実際にどれだけの貢献をしているのか,一般の人はほとんど知らないのではないか。少なくとも今の消防には,救急救命士の活躍ぶりを世間に向けてどんどんアピールしようというような意欲は感じられない。そういう状況で救急救命士のレベルアップを訴えたところで,世論の共感を得られるとは思えないのである。
救急救命士は,救急医学と救急医療をつなぐ重要な医療スタッフの一員として位置付けられている。彼らがどれだけ頼りがいのある優秀なスタッフになれるかどうかが,救急医療体制の今後を左右するといっても過言ではない。
それだけに,一日も早くパラメディック並みの救急救命士にグレードアップしてもらったほうがいいと私は思う。しかし,それにはまず,みんなに愛され信頼される救急救命士像を確立することが先である。彼らが実際どんな活動をしているのか,そしてどんな成果を上げているのかについて,積極的な情報公開をするところから始めるべきではないだろうか。 (Yuji KUROIWA)
▲図1 「激論・救急を撃つ・!)」でも日本版パラメディックの可能性を徹底討論
▲図2 シアトルの救急車を取材
▲図3 アメリカのパラメディックの活躍ぶり
コラム1:救命士法案の成立
救急救命士法は平成3年4月18日,前例をみないスピードで成立した。厚生省,自治省,自民党でそれぞれ実質的検討が始まってからわずか8か月後のことである。同じく生命にかかわる「脳死移植法案」が,常に継続審議に回され,棚晒しにされたまま,いまだ日の目をみないのとは対照的である。いかにプレホスピタルケアが時流に乗っていたかが忍ばれる。ちなみに「サリン等による人身被害の防止に関する法律(サリン法)」は,地下鉄サリン事件発生からほんの29日目に緊急上程され,即日成立した。
この法案でもう一つ注目したいのは,とかく縦割り・縄張り行政といわれるなかで,医業に対して伝統的な考え方をもつ厚生省と,市町村業務としての救急業務を主張する自治省が,搬送途上の医療の確保を標榜して協力し,法案提出したことであろう。
コラム2:国会審議点描
救急救命士の導入によって,わが国はプレホスピタルケアの柱を米国型パラメディック制に求め,フランス(SAMU)型ドクターカー制度導入を捨てたようにみえるかもしれないが,本法案の制定審議過程をよく調べると,ドクターカーの普及拡充こそ理想とし,救命士はむしろそれまでの「つなぎ」と位置付けられているようである。なお,気管内挿管の是非には国会審議上は白黒をつけていない。
国会では,「セルシン,ボスミン,ニトログリセリン,キシロカイン,プロタノールなども救命士が使えるよう検討してほしい」といった踏み込んだ指摘をする議員(常松)もいる一方で,ある議員は自分も医師だが,と前置きし,「医師でない者が注射という医療行為を行うのは問題。救命救急だから,という抜け道はけしからん。風邪引きでも何でも救命救急は必要なんです」と意味不明に憤慨している。同議員は精神科医師である。
コラム3:大蔵大臣の涙
救命士法案提出に先立つ第118回国会(平成2年5月28日)でも,常松克安議員が救急医療に対する政府の対応を追及した。最後に財政支出について答弁に立った大蔵大臣はまた,委員の質問から離れ,自分の母親がその2年前に倒れたときにDOA(CPAOA)となり,蘇生されたものの依然長期療養中であること,そして救急隊員の処置がもう少し広範なものであってほしかった,と述べた。参議院予算委員会でこの個人的感想を洩らしたときの大蔵大臣は,橋本龍太郎現首相である。