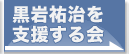
HOME > これまでの著書・コラム > 救急医療について
1.
救急救命士に気管内挿管を容認するかどうかの議論が大詰めを迎えつつある。坂口厚生労働大臣が前向きの答弁をしたことから、今、厚生労働省の検討会で6月中にも中間報告をまとめるべく作業が続いている。
大臣の姿勢が明確になっていることから、容認に向けて動き出すはずと期待されてはいるが、専門家の議論をよく聞いてみると、まだまだ予断を許さない状況のようである。メディアが気管内挿管だけをクローズアップし過ぎることへの専門家の反発も多い。さまざまなデータや情報は飛び交っているが、その真偽をめぐる議論も同時に起きており、議論は複雑化している。
私は10年前にこの救急救命士制度ができるまでの過程で、2年間のキャンペーンという形で制度誕生に深くかかわった。その時の経緯を含め私なりにこの議論を整理し、今求められている救急救命士のあるべき姿について、今日から5日間連続で論じてみたいと思う。救急救命士の気管内挿管は昨年暮れに突然、社会問題として急浮上した。秋田県内の消防本部では以前から救急救命士による気管内挿管が日常的に行われていたという事実が浮き彫りになり、センセーショナルに伝えられたからである。
そもそも気管内挿管は現行法では医師にしか認めれていない医療行為であり、救急救命士が行うことは明らかに医師法違反である。そのような法律違反行為が、秋田市消防本部で8年1月から13年6月までの5年半の間に計673人に行われていたというのだから、ある種の衝撃を持って伝えられたのはやむをえない。
しかし、その救急救命士の気管内挿管によって救われた人もいるという事実も明らかになって、議論の流れは変わってきた。しかも、秋田だけではなく、山形、新潟、青森でも行われていたことが次々に明るみに出て、問題は秋田だけの問題ではなくなり、救急救命士制度そのものが問い直される事態となってきた。
私の元へも、全国の救急救命士や救急医からたくさんのメールが届けられた。そのほとんどはこれをきっかけに救急救命士に気管内挿管を認めるように法律を改正すべきだというものだった。
私自身は救急救命士が気管内挿管を行っていたという報道に最初に接した時は、驚くとともにある種の不快感を覚えていた。これはフライングではないかと思ったのである。たとえそれでいい結果が出た事例があったと言っても、明確な法律違反に対しては安易に肯定的な評価を下すことはできない。
こういった一部の先走りが全体の流れを逆行させる危険性だって十分にある。日本における心臓移植が和田壽郎教授の一件で数十年遅れることになったと言われるが、それと同じようなことになりはしないだろうかと私はたいへん心配になった。
しかし、実際に自ら取材してみて私の思いは一変した。むしろ今回明るみに出てきた問題は起きうるべくして起きたものと言うべきなのではないだろうかということである。
救命士制度はアメリカのパラメディック制度を真似たものである。それなのにパラメディックには認められている気管内挿管がなぜ、救急救命士には認められなかったのか、そこにすべての問題の原点がある。
救急救命士以前の救急隊は心臓呼吸の停止した患者に対して、体位や顔の向きを変えて気道を確保し、手動式のバッグを使って人工呼吸を行っていた。しかし、喉に吐瀉物を詰めている患者などに、この方法で有効な人工呼吸を行うのは難しかった。より的確な人工呼吸を行うために患者の喉にチューブを通して空気の通り道を確保した上で、酸素を送り込むのが気管内挿管である。
ただ、当初より一部ドクターたちはこの気管内挿管の技術的な困難さを強調し、救急隊に認めることには強く反対をしていた。ところが議論の最終局面になっていきなりラリンゲルマスクや食道閉鎖式エアウェイなどという代替物が唐突に持ち出されてきた。
これら代替物がどれだけ気管内挿管の代わりになるものなのかという医学的検証はほとんどなされないまま、「器具を使った気道確保」という表現で賛成派と反対派が折り合ったのである。「器具を使った気道確保」という内容さえ法律の本体に盛り込んでおけば、後からでも気管内挿管に変更できるだろうという知恵であった。
制度を作ることを優先したということでは評価できるだろうが、要するに足して2で割る妥協だったということである。気管内挿管の問題に真正面から取り組むことを避けて、肝心な問題は先送りし、理念よりも結果を重視したきわめて日本型決着が、今になって大きな問題となって出てきたということなのである。
2.
平成13年12月20日、東京上野の寛永寺輪王殿では日本の救急医学界の重鎮、日本医大病院理事長の大塚敏文教授の葬儀がしめやかに執り行われていた。その参列者席の最前列には坪井栄孝日本医師会会長の姿があった。
大塚教授と坪井会長は日本医大の同窓であったが、かたや日本の救急医療のリーダーとして新たな歴史を作り、かたや日本医師会の頂点を極めたまさに両雄であった。その二人が今このような形で向き合っている様を私は感慨深い思いで見つめていた。
平成2年9月、「激論!救急を撃つ」と題した特別番組で、二人は私の目の前で激しい議論を闘わせた。「アメリカのパラメディックのような高度な救急隊を作って気管内挿管を認めるべきだ」とする大塚氏に対し、当時、日本医師会救急担当常任理事だった坪井氏は「医師でない者に医療行為を認めるわけにはいかない。ましてや救急隊の気管内挿管は危険性の方が高い」と強硬に反対論を展開した。
結局その時の討論が救急救命士制度誕生につながる最終局面となったのであったが、と同時に、それが救急救命士の行える処置から気管内挿管がはずされる最後の決着の場ともなったのであった。
この番組の収録が行われたのは、救急隊の処置範囲拡大に向けて、消防庁、厚生省のそれぞれの検討会の中間報告がまとめられた直後であった。「今の救急隊に高度な応急処置を認めるべき」という消防庁案に対し、厚生省案は「あくまでドクターカーを基本とし、高度な応急処置のできる救急隊については新しい医療関連資格を作るなら検討の余地あり」というものであった。
両案とも「高度な応急処置のできる救急隊を作る」という点では一致していた。「高度な応急処置」とは点滴・除細動・気管内挿管の「救命の3点セット」と呼ばれるものである。これらはいずれも医療行為に踏み込む処置内容であったが、日本医師会がそれを容認する方向性を見せていたのは大きな前進であった。しかし、3点の中で最も反対意見の多い気管内挿管まで踏み込めるかどうかが最大の焦点となっていた。
スタジオには二人の他に、自民党の丹羽雄哉氏と麻酔学会会長の清野誠一氏(故人)、両省の担当課長がそろっていた。丹羽氏は自民党の救急医療問題小委員会の委員長として、とりまとめの任にある立場であった。ちょうどこの番組には彼が調整すべき人物が揃っていたのである。
気管内挿管をめぐる最後の攻防は、本当は番組上ではなく、収録前の楽屋裏で行われていた。その日、出張先から駆けつけることになっていた日本医師会の坪井氏が、悪天候のために飛行機が遅れた。そのためゲストはいくつかの応接間に分かれて待つこととなった。その約1時間半ほどの時間を利用して、丹羽氏は部屋を行ったり来たりして調整を計り、最終案をまとめたのである。到着した坪井氏にも了解を取り付けた丹羽氏は、本番直前の私の耳元で囁いた。
「黒岩さん、今、まとまったから。ただし、2・5点セットだな」
「2・5点セット」とはいったいなんなのか。「救命の3点セット」はどうなったのか。キョトンとしている私に向かって彼はこう言った。
「『気管内挿管』はやっぱりダメだなあ。これは麻酔科も絶対ダメだと言って譲りそうもないんだ。これを押し通すかぎり、まとまらないよ。その代わりなんとかマスクとかあるそうだね。あれでも同じようなことができるって言うから、『器具を使った気道確保』という形でいく。だから2・5点セットだね」
本番のスタジオにこれから向かうというギリギリの状況ではあったが、私は反射的に答えていた。
「ダメですよ。そんな2・5点なんて。せっかくここまできたんだから、『気管内挿管』でいかなきゃダメ。あくまで3点セットですよ」
一緒にスタジオに向けて歩きながら、丹羽氏は苛立たしそうに話した。
「絶対、無理。3点にこだわっていると、全部なくなっちゃうよ。とりあえず、『器具を使った気道確保』として置けば、そのうち、器具として気管内挿管の器具を使えるようにしていけばいいじゃない。ただし、今日の番組ではそこまでは言えないけどネ。」
そんなやりとりをしながら入ったスタジオで、収録が始まった。他のゲストに確認する余裕もなかったが、私の前に並んだ6人のゲストの間ではすでに合意ができあがっていたのである。番組の議論自体はそれぞれの立場の違いが浮き彫りになり白熱したものとなったが、私は葬り去られた気管内挿管が禍根を残すことになるのではないかと不安でいっぱいだった。
丹羽氏は番組中では、「次の国会で自民党案を出す」と明言し、翌日のニュースを飾った。これが救急救命士法案となって成立していくことになったのである。
3.
「黒岩さん、聞いて下さい。僕たちがどんな気持ちで気管内挿管をやってきたか・・・。まるで僕たちが悪いことをしてたかのようにも伝えられていますが、これまで人の命を救おうと一生懸命やってきたすべてが否定されているようで、いたたまれないんです。僕たちの生の声を聞いてくれませんか?」
昨年の暮れ、せっぱ詰まった声で私の元へある救急救命士から電話が入った。救急救命士による違法な気管内挿管が行われてきたことが明らかになった地域の救急隊員であった。会ったことはなかったが、名前は聞いたことがある気がした。以前に私の元へ手紙をくれて、何度か手紙のやりとりをしたことがあったからだった。
近いうちに私の方から出向くから話しを聞かせて欲しいと電話越しに伝えたが、彼は自分で行動を起こさなければ気がすまない、自分の休日を使って私に訴えに行きたいからぜひ会って欲しいと言って譲らなかった。
数日後、彼は言葉どおりに私の目の前に姿を現した。いかにも生真面目で、純朴そうな青年であった。その表情を見た瞬間、結果としては法律違反であっても、その行為の背景には彼のひたむきな思いしかなかったことを確信した。
秋田、山形、新潟、青森などの各県で、公的機関である消防本部がなぜに法律違反を堂々と続けてきたのか。それは今もって理解に苦しむところだが、少なくとも消防本部自身がリードしたのではなかった。主導したのはドクターサイドであった。救急救命士の教育にあたったドクターが自らの判断で救急救命士法の一線を越え、それを消防側が無批判に受け入れてきた結果であった。
秋田では平成4年に誕生した救急救命士の第一期生から、気管内挿管を行っていた。それを強力に推し進めたのは当時、秋田大学病院救急部にいた熱血漢ドクター円山啓司氏であった。彼が自ら率先して救急救命士に気管内挿管の手技を教えたのである。
円山氏も法律上は救急救命士に気管内挿管が認められていないことは十分認識していた。しかし、心肺停止状態の患者に対して気管内挿管をすることは絶対に必要だという救急医としての信念から、あえて一線を踏み越えたのである。気管内挿管への一部専門家の抵抗が強かったのはその技術的困難さからであったが、円山氏はしっかりと病院実習さえすれば、医師でなくとも技術そのものを身につけることは可能であると判断した。
そして、円山氏は彼らを手術室へ招き入れて、全身麻酔を受ける患者に対して実習を行わせた。人形を使っての実習と平行して、生身の人間に対して気管内挿管実習を繰り返すことによって、救急救命士は高い技術を身につけていった。そして彼らは病院実習で最低30例ほどの挿管を体験した上で、救急隊として現場配属されていったのである。
円山氏は彼らが実習を終えて病院を離れた後も徹底的に面倒をみた。「管内の救急救命士は自分が責任を持って一人前にしてやるんだ」という熱い思いから、その後も彼らを折りに触れては病院内に呼び込み、搬送後の患者がその後どうなったかについて教えた。そして実際の救急患者に対して医療サイドはどんな取り組み方をしているかを伝えようとした。
「救急救命士は消防の職員ではあるがれっきとした医療従事者である」という意識を徹底させた。特に自分の教え子が救急出動現場で初めて気管内挿管を経験するまでは気になってならなかったと言う。初めての挿管事例に対しては一人一人の救急救命士の処置に事後検証を行い、丁寧な論評を書いて励まし続けた。
「今回は私自身学ぶべきことが多かった症例でした。私が挿管だと言ったにもかかわらず、吸引を最初に行い、それから挿管を行ったのはよい判断だと思います。また、現場での血管確保を指示したにもかかわらず、搬送を考え、車内で血管確保すると言ったこともよい判断でした。医師が何を言おうと、自分の信念に基づいて行動したことは高く評価できます。これからも自分の考えで信念をもって救急現場で活躍されることを望みます。」
救急救命士たちはその心のこもった論評を涙を流しながら読み、自分の宝物にしていたと言う。
円山氏はしばしば救急救命士と酒を酌み交わしながら救急医療について語り合った。そういう地道な努力の積み重ねの結果、この地域ではまさにドクターと救急救命士の顔の見える関係が出来上がっていたのである。
ところが救急救命士の気管内挿管の事実がセンセーショナルに伝えられるやいなや、厚生労働省は業務範囲の逸脱防止を求める指導を強化した。そして、秋田市消防本部においても救急車から気管内挿管の器具がいっせいに降ろされてしまった。これによって救急救命士による気管内挿管は一気に封じ込められることとなってしまったのである。
4.
救急救命士が違法な気管内挿管を行なっていたことが発覚した秋田市消防本部などでは、もちろん今は行なわれていない。法律違反が明らかになったのだからやむを得ないことだろう。
しかし、「それら消防本部は人の命を救うために、これまで確信犯的に違法行為を行ってきたはずだ。それが、ばれたからすぐに方針転換というのではあまりにも不甲斐ない。この際、国の方針に逆らってでも、毅然と継続を決めるという選択肢は取れなかったものか!」と、思わず言いたくなってしまうのは私だけだろうか。
本来の地方分権とはそのように中央との闘いによって獲得していくものではないかと私は思うが、今の自治体にそこまで要求するのは酷ということだろうか。
かつて気管内挿管を実施していた救急車には、今は法律に定められたとおり、代替物のラリンゲルマスクや食道閉鎖式エアウェイのチューブが積み込まれている。秋田市で救急救命士に気管内挿管を教え続けてきたドクター、円山啓司氏の下へもチューブをつけた状態の患者が運び込まれてくるようになった。
「こんなんじゃダメなんだ!」と怒鳴りながら、チューブを引き抜き、気管内挿管に変える彼の姿が目撃されたと言う。それは気管内挿管の手技をマスターしていながら、チューブを使わざるをえなかった救急救命士にとっても無念の思いは同じだったようだ。
チューブをつけて運ばれてきた患者は病院到着後、そのままの状態で治療が行われるわけではない。必ず、チューブをはずして気管内挿管に変えられるのである。それが救急救命士が現場で気管内挿管をするべきだという主張の根拠にもなっている。
私に向かって涙を浮かべながらある救急救命士は語った。
「ドクターに引き継いできちんと挿管をしていただけるならまだしも。チューブを抜いた後、気管内挿管をしようとしても、うまくできないドクターが大勢いるんです。私の目の前で、ドクターが挿管にてこずり、結局、血だらけにしちゃったっていうこともありました。私ならできるのにって思うと悔しくて悔しくて・・・、でも私たちは黙って見ているしかできないんですからね・・・」
ある病院の調査によると、気管内挿管を任せられるドクターは30%くらいしかいないという。気管内挿管とは医療行為におけるひとつの手技である。トレーニングしているかいないかが最大の決め手になるのであって、医学的知識の多寡が問われるべき性質のものではない。
現に世界中のパラメディックは、ドクターでなくとも十分なトレーニングを積んだ上で気管内挿管を実施している。ドクターだからできる、ドクターでないからできないというわけ方ができるものではない。ところがそういう事実を受け止めようとしないドクターは今も少なくないようだ。
4月25日、東京・信濃町で開かれた日本臨床救急医学会での「救急救命士の気管内挿管についての緊急討論」は、学術的な学会とは思えない異様な熱気に包まれていた。厚生労働省の検討会の報告書を取りまとめた千葉大大学院集中治療医学の平澤博之教授の発表は、本人は科学研究にすぎないことを強調してはいたが、会場の救急救命士の神経を逆なでするに足る厳しい内容であった。
平澤氏は救急救命士や海外のパラメディクによる気管内挿管の有用性を過去20年間の文献などから調査した結果、「救命率向上に寄与したとの医学的根拠は存在しなかった」と断定した。さらに「パラメデイックによる気管内挿管で救命率が悪化するとの報告も存在する」であるとか、「米国心臓協会(AHA)では救急現場で行われる気管内挿管の危険性を指摘している」など、ネガティブな報告を数え上げた。
その上で、今の救急救命士に認められている代替物での気道確保で十分だと結論づけたのである。救急救命士の気管内挿管容認への流れを断ち切ろうとするかのような内容で、私も思わず会場から発言をした。
そもそもパラメディックの気管内挿管だけに焦点を当てて重箱の底をつつくような調査をすることにどれほどの意味があると言うのか。気管内挿管の効果を研究するならドクターのそれも同時に行なうべきである。もし、本当に気管内挿管に効果が少なく、危険性が高いというなら、ドクターにも止めさせるべきではないのか。
現場での挿管の危険性を言うなら、フランスのようなドクターカー先進国でも止める動きが出てしかるべきである。要するにドクターの挿管は安全で、パラメディックの挿管は危険であると言いたいだけのようだ。しかし、挿管ができないドクターが大勢いるのが現状であるということをどう説明しようというのだろうか。
今はどうすればよりハイレベルの救急救命士ができるかを論じるべき時である。ドクターの意識改革も同時に求められているように思えてならない。
5.
救急救命士は制度ができて10年、これまで先送りし続けてきた宿題を今こそ仕上げる時を迎えている。連載の最終回にあたって、私は救急救命士の新しい姿として「スーパー救命士構想」を提言したい。
その前提として、秋田市消防本部などで行なわれていた違法気管内挿管については、法律違反は法律違反としてきちっとケジメをつけるべきだと思う。違法でも命を助けようという善意でしたことだからいいだろうというような論調が、議論を複雑化させているように思えるからである。
船橋市立医療センターの金弘氏もこの点を強く主張する。金氏らはこの10年間、ドクターカーに救急救命士とともに乗り込んで、救命率向上のために全力を尽くしてきた。それは現行法の中でどこまでやれるかを、スタッフの熱意と献身によってギリギリまで追求してきたものであった。それだけに、違法行為をしていた秋田市の関係者たちが、悲劇の主人公のように扱われることに強い不快感を覚えるのは当然と言えよう。
ケジメのつけ方にあえて言及するつもりはないが、いったんケジメをつけた上で改めて秋田市などでの10年にわたる救急救命士の気管内挿管の歴史から何を学ぶことができるかを検証すべきであると思う。救急救命士により確かな気管内挿管を身につけさせるためのノウハウは、貴重なデータとして山のように眠っているはずである。
秋田市が救急救命士全員に気管内挿管を認めていたからといって、現在、全国に約1万人いる救急救命士全員に今すぐ気管内挿管を認めるというわけにはいかない。それだけの研修の場を確保することはできそうにない。
そこで「スーパー救命士」を提言したい。選抜された救急救命士に対して、気管内挿管などの実技を中心にした特別なトレーニングを行なった上で、麻酔学会や臨床救急医学会などが認定するのである。
「スーパー救命士」には気管内挿管だけでなく、一部の薬剤投与まで認めるべきである。要するにアメリカのパラメデイック並みの救急救命士を新たに作り、救急救命士を二層構造にするということである。
そのためにはさらに2年間の専門教育が必要だなどと言うドクターもいるが、それでは現実的解決策にはならない。あくまで実践を積み重ねた救急救命士のステップアップの方策と位置づけるべきである。法律本体の改正までは必要ない。
研修期間については、秋田市では全身麻酔を受ける患者を対象にした手術室での臨床実習を30例程度行っていたというから、それはひとつの参考となるだろう。当然、患者に対して説明し、同意を得ることも必要となるため、養成数に限りがあるのはやむをえないだろう。しかし、その限定された条件の中で、できうるだけの人数を養成するべく知恵を絞る余地はありそうだ。
本来は船橋市のように、ドクターカーでドクターと一緒に行動しながら研修するのが理想だろうが、それはひとえにドクターの熱意にかかっている。
また、「スーパー救命士」には資格取得後も、継続的な病院研修を義務付ける必要がある。自らが実施した気管内挿管をドクターとともに検証しなければならない。ドクター側の負担も大きいが、それだけに医療関係者と救急救命士がこれまで以上に密接で良好な関係を作っておかなければならない。
救命の実を上げるために最も大事なことは「救命の鎖」をつなぐことである。心肺停止で倒れた人の隣にいる一般市民が心肺蘇生法を行い、救急隊が高度な応急処置をし、そして医療関係者に引き渡す。それぞれが鎖のように結びつき、連携することによってこそ、効果が上がるというものである。
秋田市から学ぶべき最大のポイントは、実はこの「救命の鎖」にある。救急救命士への気管内挿管を主導した元秋田大学病院のドクター円山啓司氏は、実は「救命の鎖」を作った功労者であったということを忘れてはならない。
かつてこの地域で、用水路に落ちた幼児を、近くの老人たちが心肺蘇生法を行って蘇生させたという感動話を取材したことがあったが、彼らはみんな心肺蘇生法を身につけていた。それは円山氏らが続けてきた一般市民向けの心肺蘇生法の講習会の成果であった。
円山氏が救急救命士と顔の見える関係を作り、手作りで彼らを育てていたという話を前に紹介したが、これは医療関係者と救急隊の鎖をつなぐ地道な努力だったのである。
救急救命士のあり方の議論は、気管内挿管だけが突出し、挿管さえ容認されれば、救命率は一気に上がるかのような期待感がふくらんでいる向きもある。しかし、もっとも重要なことはこの「救命の鎖」であることを強調しておきたい。
まずは「救命の鎖」をしっかりと作った上で、それに支えられた形で気管内挿管もできる「スーパー救命士」を作るというのが、今の救急救命士に求められている改革の姿であると私は思うのである。