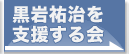
HOME > これまでの著書・コラム > NURSE SENKA
4月、東京原宿の表参道の一等地に日本看護協会の新しいビルが完成し、そのお披露目のパーティーに出席していたときのことです。会場ではたくさんの懐かしいみなさんと再会できたのですが、とりわけ日本赤十字看護大学の教授に転進された川嶋みどりさんとの再会は、新たな取材につながりました。
私が「さまよえる医療難民」というテーマで、パーキンソン病患者さんの実態を取材しているとお話ししたところ、即座にこんなリアクションがありました。
「それなら、私がやっている看護音楽療法を取材して下さいよ。とっても感動的だし、面白いわよ」
聞き馴れない「看護音楽療法」という響きに引かれた私は、その場ですぐに取材を確約しました。黒岩祐治のメディカルリポート「さまよえる医療難民」シリーズの4回目は、こうして少し切り口を変えた内容で放送することになったのです。
「川嶋流看護音楽療法」のポイントは単に音楽を使った療法というのではなく、音楽とトランポリン運動を組み合わせているところです。場所は東京・足立区の柳原病院の会議室。音楽はピアノとハープ、部屋の真ん中に置かれたトランポリンの周りを10人のナースが取り囲みます。トランポリン運動の前に、患者さんの体調検査をした後、温かいお湯を使ったマッサージで体をほぐし、慎重な準備を行ないます。その上でナースたちが患者さんを背後から抱えて、トランポリンの上に移します。そして、ナースたちはピアノ演奏に合わせて、患者さんの体をしっかりと支えながら静かに上下に揺らせます。
この日は中年男性患者さんの趣味に合わせて、ジャズが使われました。ナースたちも一緒になって指でアフタービートのリズムを刻みます。ちょっとしたジャズ喫茶のようないいムードです。表情の固かった患者さんでしたが、明らかに変化が生じてきました。関わってるナースたちもみんな楽しげです。
トランポリンの振動によって、患者さんの体は緊張しますが、それがかえっていいのだそうです。日常生活の中では味わえない浮揚感を体験することができて、患者さんの気持ちが解放されてきます。
また、揺さぶられることによって膝の神経が刺激され、それが脳に伝わり、記憶や感情を司る部位が刺激されます。
トランポリン運動を行なった後、患者さんはマットの上に横になり、今度はハープの静かな演奏を聴きます。刺激した後、瞑想することによって眠っていた情感を呼び覚ます効果があるのです。優しい表情の出てきた患者さんの眼からは一筋の涙が頬を伝わりました。とても感激されているようでした。
ナース自身が撮影した記録用VTRには、これまで全く反応のなかった患者さんが、ナースの「気持ちいい?」との問いかけに、指を立ててしっかりと意思表示をしている様子が写し出されていました。それを見たナースが感激して泣いている声も収録されていました。また、別のVTRには、看護音楽療法を終えた患者さんがピアノの連弾をしているさまが写っていました。この人は元はピアノの先生でしたが、病気になってからはピアノを弾こうともしなかったそうです。それがまるで別人のようにピアノに向かっているのです。
また、小さく震えるような字を書いていた人が、療法後はダイナミックでしっかりとした字を書くのには驚きました。お化粧もしなくなって怖い顔ばかりしていた高齢の女性患者さんが、この療法を8回くらい行なった後、化粧をし始め、マニュキュアまでするようになったそうです。
このように効果は見ただけでも明らかですが、病気そのものがよくなっているわけではないそうです。パーキンソン病は進行性であって、よくなることはないのです。ただし、和田秀樹氏によると、病気によって意欲を失ったり、抑うつなどの合併症を併発していることが多いのだそうです。つまり、パーキンソン病そのものの症状以上に、心を閉ざすことによって悪い症状が加わっているのです。それが「看護音楽療法」によって、心に働きかけて意欲を回復することで、症状が改善するのです。
こういった発想は医学的な治療行為という概念にはありません。それゆえ、「看護音楽療法」は治療行為の一貫として認知されておらず、当然、診療報酬の対象ともなりません。ですから、ナースのボランティア的な試みとしか位置づけられていないのです。これまで川嶋さんは厚生労働省の研究費や、生命保険会社の研究助成金などを確保しながら、運営してきましたが、今は患者さんから2000円をもらって、演奏者の実費に当てているそうです。
「有効な治療に関して支出できるようなシステムが必要ですね。そのためには有効性を評価するシステム作りから始めなければなりません。医師は検査数値ばかり見て評価しようとしますが、特に神経難病の場合、それだけではふさわしくありません。意欲だとかやる気だとか、そういったものも包括的に評価の基準にしていくことが必要ではないでしょうか」
和田さんはそう主張します。つまり素人目には明らかに回復の後が見えると感じるものを、いかに客観的な基準にしていくかということでしょう。
また、こういった療法を制度化するための方策のひとつとして、音楽療法士という国家資格を作ろうという動きもあります。ただ、川嶋さんのようにナースの立場から、演奏者との協同で音楽療法をしたいと考えている人もいれば、音楽療法士とは自らが演奏できなければいけないと考える人もいます。このあたりの調整が必要なようです。
新しい試みであるこの「看護音楽療法」を一般化することができれば、パーキンソン病患者にとっては朗報になるに違いありません。そのためにはまず、こんな療法があるということをより多くの人に知ってもらうことから始めなければなりません。今回の番組とこの記事がひとつのきっかけになればと願っています。