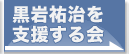
HOME > これまでの著書・コラム > NURSE SENKA
余命3カ月と宣告され「家に帰って好きに」と半ば強制的な退院へ
「さまよえる医療難民」ということで、これまで番組ではパーキンソン病やALSという非常に厳しい難病患者の置かれている現状をリポートしてきました。しかし、私たちにとってもっとなじみのある病気であるがん患者も、末期になるとさまよわざるをえない現実がありました。
福島県南会津郡の大竹美枝子さん(当時58歳)が余命3カ月を宣告されたのは、2002年の5月のことでした。胆管がんがリンパ節にも転移していました。病院からは半ば強制的に退院を迫られました。
「家に帰っていいですよ。自由に好きなことをしていてください」
そのように言われたそうですが、大竹さんは「要するに病院から見捨てられたんだな」と感じたそうです。好きなことをしろと言われても、治療を放棄されたような状況では黙って死を待っていろということなのか、一家は絶望の淵に突き落とされました。
そんな時に救いの手を差し出したのが、キャンサーフリートピア代表で、外科医の土屋繁裕さんでした。末期がん状態になった時に、大竹さんのように病院から放り出される患者さんはたくさんいます。そんな人たちの力になりたいという思いから、土屋さんはこの活動を始めました。ここは末期がんに苦しむ患者さんたちの駆け込み寺のようになっていました。
土屋さんは一日数人しか患者を診ません。その代わりに一人一人からじっくりと話を聞きながら、治療を進めていきます。特に彼が実践しているのは「休眠療法」と呼ばれるものでした。がんを徹底的にたたくのではなく、現状維持を目指す方法です。そのために抗がん剤を控えめに使い、腫瘍マーカーの数字を見ながら、コントロールしていくのです。
息子さんの結婚式と娘さんの入学式出席という目標を実現
大竹さんは余命といわれたタイムリミットから3カ月後の11月30日に息子さんの結婚式を控えていました。「なんとかして結婚式に出たい」大竹さんはその目標に向かって土屋病院に通い、治療に専念しました。すると当初5000を超えていた腫瘍マーカーの値がどんどん下がり始め、なんと1000を切るまでになりました。
そして、念願の結婚式に出席し、幸せそうな息子夫婦の姿をその目で確認し、祝福することができたのです。特別に母親のスピーチの時間も設けられ、美しく感動的な披露宴となりました。大竹さんは土屋先生との二人三脚で、奇跡を実現させました。目標を持って生きることがいかに大事であるか、データの上にもはっきりと表れていたのです。
しかし、データは残酷でもありました。結婚式が終わった後、再び数値が上昇し始めたのです。目標の達成感は生きる力にはつながらないようでした。傍目で見ていても気の毒なくらい、具合が悪そうになっていきました。腰の痛みと吐き気で、イライラが募り、家族にきつくあたることも多くなりました。
そんな彼女を消防官のご主人は優しく、包み込むように接していました。温かい家族だからこそ、わがままも言えたのでしょう。しかし、大竹さんは自分で次の新しい目標を見つけ出しました。それは来春、高校を卒業して東京の大学に進むことになっている長女の東京の生活を見届けたいというものでした。
するとデータは再び驚くほどに改善され始めたのです。卒業式の日は体調がすぐれず、出席はできませんでした。しかし、大学の入学式には福島から新幹線で上京し、夫婦そろって出席することができました。娘の新居も確認し、新しい友人たちに挨拶をすることもできました。
結局、大竹さんは3カ月と宣告された余命を大幅に伸ばし、1年8カ月後に亡くなりました。具体的な目標を持って生きようとする強い思いは、余命を伸ばす大きな力になるということを、身をもって私たちに教えてくれました。
患者さんの気持ちに寄り添い、がんと闘い余命を大幅に伸ばす
振り返りのVTRを見ながら、土屋さんはスタジオで目に涙を浮かべていました。これまで数え切れないほどたくさんの患者の死に向き合ってきた医師がこういうシーンで涙を浮かべるのはとても珍しいことです。いかに土屋さんが家族のような気持ちで接していたかが伝わってくるようでした。
「そもそも医師が伝える余命というのは、何を根拠に言っているんでしょう。本当に知りたいと思っている患者さんは少ないんです。あたるかどうかも分からないのに、そういうことを言うことで、患者はどんなに苦しめられることか。私は言うべきではないと思います」
和田秀樹さんは次のように指摘しました。
「研修医の教育の中では、余命は厳しめに言っておけと指導されているんです。言った余命より早く亡くなったら、責任を取らされるからというんですよ」
余命を告げる方はそれでいいかもしれませんが、告げられた方はそれで人生が大きく左右されてしまいます。しかも、そういう患者に対して土屋さんのように親身になって支えてくれる医師がいればいいですが、なかなか見つけることができないのが現実です。土屋さんのように一人の患者にたっぷり時間を割いても、収入は全く増えないのですから、やむをえないのかもしれません。
「私は実家が病院をやっていますから、採算は合わないけれどボランティアでやらせてもらってます」
自由診療でやればできるのでしょうが、土屋さんはあくまで保険診療の枠内でボランティア精神によって実践していたのです。要するに、これも診療報酬体系の中でいかにして医療の質を担保するのかという本質的な問題です。最も肝心なところを医師の善意に頼るしかないという現状を、私はいつまでも放置すべきではないと思います。
ところで、この番組を収録して約2カ月後、突然、土屋さんの訃報が届きました。くも膜下出血で倒れ、意識が戻らないままに亡くなったそうです。とってもお元気で、兆候など全く感じられなかっただけに驚きました。49歳の働き盛りで、しかも患者の気持ちに寄り添いながら、共にがんと闘っていた素晴らしい医師を失ったということは、日本の医療における大きな損失であったと思います。ご冥福をお祈りするとともに、彼の思いをカタチにしていかなければならないという思いを新たにした次第です。