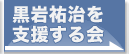
HOME > これまでの著書・コラム > NURSE SENKA
末期がん患者の退院後に向けてのきめ細かいフォロー
「先生、在宅医療ってやっぱりいいもんですねえ。ご飯は食べさせてもらえるし、風呂には入れてくれるし、掃除はしてくれるし、最高ですよ」
前立腺がんの92歳の男性患者が、往診に出向いた要町病院の吉澤明孝副院長に語りかけているさまは、まさに実感がこもっていました。どんなに素晴らしい病院であろうと、自分の自宅に勝るものはありません。
特に終末期を迎えたがん患者の場合には、病院にいても積極的治療をするわけでもないわけですから、自宅のほうがいいに決まっています。しかし、みんなが望んだからといって、だれにでもできるというものではありません。今回の「メディカルリポート」では、末期がん患者が在宅医療を受けるための課題について考えてみました。
癌研有明病院では、手術を終えた乳がんの39歳の女性患者に退院後の療養について、ソーシャルワーカーが説明をしていました。
「そのまま退院してよろしいということでしたから、私のほうでご近所の病院を探して、交渉をしました。徳洲会病院の内科の先生がお宅まで訪問可能ということでしたから、お願いしておきました」
大きながんの専門病院を退院した後の行き場がなくて、さまよう患者が多いことはこれまでも指摘してきました。それだけにこういったキメの細かい対応は、患者にとってどれだけ大きな支えになることでしょう。
この患者は自宅で酸素吸入器を使うと高い金がかかるのではないかと心配していました。しかし、それは保険でレンタルできるものでした。相談したからこそよかったものの、知らないままだと呼吸が苦しいのを我慢するようなことになっていたかもしれません。
条件はキーパーソン、痛みのコントロール、訪問ステーションとの連携
吉澤さんは年間100人以上の在宅患者を診ています。年間訪問回数は2,000件を超えるといいます。しかし、一人の医師で在宅患者すべてをフォローすることはできません。そこで訪問看護ステーションのナース、青出木えみ子さんと連携しながら、在宅医療を実践しています。
80歳の子宮がんの患者は、娘さんが看病にあたっていました。「今は食欲がなくて、スープとプリンしか食べないんですよ。いろんな薬がありますけど、全部飲まなきゃダメですか? せっかく寝てるのに起こさなきゃいけないのはかわいそうだし、眠いときに起きてトイレに行くのも足元がふらついて危ないんです」
在宅ならではの気軽さもあってか、患者やその家族はいろいろと具体的な相談事をぶつけてきます。
この患者は皮膚に貼るだけでモルヒネと同じ効果の出るフェンタニールパッチを使用していますが、吉澤さんは痛みのコントロールがうまくいっているかどうかを改めてチェックしながら、質問に一つ一つ丁寧に答えていきます。
「寝てるのを起こしてまで、全部の薬を飲まなくてもいいですよ。今は転ぶのが怖いですからね。オムツしておきましょう。最初は変な気持ちがするかもしれませんが、大丈夫ですよ。その方が安心ですよ」
在宅医療がうまくいくための条件について、吉澤さんは次の3点を指摘しました。
まず、第一にキーパーソンとなって支える家族、あるいは介護者がいるかどうか。第二に痛みがコントロールできるかどうか。第三は訪問看護ステーションと連携ができるかどうか。こういった点がそろっていないと、本人がどんなに希望をしても難しいといいます。
末期がん患者の在宅医療がうまくいっていても、最期の段階でまた病院に運ばれ、そこで死を迎える場合も少なくありません。せっかくならば自宅のベッドでそのまま、最期を迎えたいというのは患者、家族の共通の願いでしょう。
だからこそ、青出木さんは在宅医療で診ていた患者を在宅のままで看取ることができたとき、言いようのない達成感を味わうことができるのだそうです。家族みんなで患者を看取ろうと言って、患者の周りを取り囲んで、頬ずりしたり、ありがとうと言いながら、臨終のときを迎えるのだといいます。
「キーパーソンがしっかりしていれば必ず自宅で看取れます。何百人と自宅で看取ってきましたが、ご家族のみなさんも含め、達成感は100%といってもいいですよ」
「ずっと診ているとそのときは患者さんが知らせてくれます」
しかし、看取るということは死の瞬間にまさにその場にいなければならないわけですから、たいへんです。ドクターもナースも生身の人間ですし、他にもたくさんの患者さんを抱えています。それなのにそんなにうまくいくものなんでしょうか? 病院でも「危篤」と言われて親戚一同が集まりはしたものの、また持ち直して解散するなんて話もよく聞きます。
吉澤さんは面白いことを言いました。
「本人が知らせてくれるんですよ。医学的なものではないんですが、本人から『お世話になりました。ありがとうございました』なんて切り出されることがよくあるんです。あ、お迎えが来てるのかなって思うんですけどね。そういうことも患者さんをずっと診ていると分かるんです」
青出木さんは家族にはきっぱりと言うそうです。
「いよいよカウントダウンに入ったなって思ったら、ご家族には会社を休んでもらいます。顔を見るのは今日しかありませんよって言ってね。そして、吉澤先生にご連絡すると、『じゃ、行くよ』っていい感じで来てくださるんです。こういうドクターがいらっしゃるからこそ、自宅での看取りは可能になるんですよ」
吉澤さんは言います。
「入院していれば症状の変化があれば、すぐにナースは来てくれる、ドクターも来てくれる。在宅はそういうわけにはいきません。病院では規則正しい生活を強制されますが、在宅では自分の勝手気ままにしてればいい。それぞれに利点、欠点があると思うんですね。患者本人、主介護者がどう判断するかによって違ってくると思います」
がんは痛みのコントロールさえできれば、他の病気に比べて在宅死を迎えやすいともいえます。そのためには、自分の生活を犠牲にしてまでも患者のために働こうという心あるドクターやナースの存在が不可欠です。そういう人材をいかに育てていくか、つまるところ教育のあり方そのものから改革していく必要がありそうです。