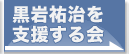
HOME > これまでの著書・コラム > NURSE SENKA
コミュニケーションがとれないと診療を拒否された在宅ALS患者
今後もっともっと在宅医療を普及させていこうというのが厚生労働省の基本的な方針です。高齢社会が進む中で、病院に患者があふれかえるような状況になれば、どんなにマンパワーを充実させても追いつくはずはありません。そのために在院日数を減らし、医療の効率化を進め、在宅医療を充実させていこうというわけであって、当然といえば当然です。
しかも、患者も在宅で診てもらえるのならその方がいいと思う人もたくさんいるでしょう。しかし、在宅医療の現実に目を向けてみると、寒々とした現実が浮かび上がってきます。現状のまま推移すれば、多くの患者が病院から追放されるだけになってしまう危険性さえあります。まさにさまよえる医療難民の大量発生です。
在宅医療を受けている50代のALS患者さんが、耳鼻科での診療を拒否されたという話を聞きつけました。彼は人工呼吸器をつけて寝たきりの状態ではありますが、足の指を使って音声変換パソコンを操り、自由に会話することができます。それどころか、今も会社の経営にあたっているというから驚きです。パソコンを駆使して、社員にさまざまな指示を送っているのです。
「のどに炎症がおこっているのは間違いない」と彼自身が訴えたことから、介護にあたっている奥さんは耳鼻科に連れて行きました。ところが、人工呼吸器をつけた患者は診たことがないということで、追い払われてしまいました。コミュニケーションも取れないだろうと勝手に解釈されてしまったことも原因だったようです。
以前にこの患者さんを診ていた大和田潔医師がたまたま訪問をしたついでに、診察してくれました。「痰が喉の奥に貯まっているので、耳管を押して少し炎症を起こしているかもしれない」とのことでした。大和田さんは言います。「ALS患者さんの耳だからといって特別なことは何もないですよ。耳鼻科の先生が普通に耳を診てくれればすんじゃう話なんですけどね」
大和田さんはALS患者の治療を数多く手がけてきましたが、在宅に戻った患者さんがこういう診療拒否に遭うことは少なくないようです。医師が拒否するだけでなく、ビルの中で開業しているクリニックなどでは、そもそもベッドがエレベーターに入らなかったり、バリアフリーになっていないために、その場所にたどり着くことさえできない場合もあるのだそうです。
かかりつけ医と専門家の地域連携があって安心できる態勢が実現
安心した在宅医療を実現させるためには、在宅で起きた新たな事態にうまく対応できる仕組みができていなければなりません。本来はかかりつけ医がいて、そこからいろんな専門家と連携してもらうカタチができているべきなんでしょうが、その連携がなかなかうまくいかないようです。特に耳鼻科の場合、もともと往診する医師も少ないために盲点になっているようです。
栃木県小山市でクリニックを経営し、在宅医療を15年にわたって専門的に実践してきた太田秀樹医師は、地域連携の必要性を強調します。地域連携のないまま患者を在宅で診るということは、回復可能な患者をみすみす見殺しにする危険性もあるといいます。
がんの末期患者の場合は、病状がだんだん進行していきますから、在宅での看取りがうまくいくケースもたくさんあります。しかし、病気になった高齢者がみんな死に向かっているわけではありません。適切な治療を施せば、治る患者もたくさんいます。それなのに家族の勝手な解釈で老衰だからということで、積極的な治療をせず、回復のタイミングを逸してしまうこともよくあるそうです。太田さんは「みなし末期医療」という表現を使って警鐘を鳴らしています。
在宅で経管栄養管理をしている患者などの場合、医療者の訪問だけでは十分でないために、特に介護者には大きな負担がかかります。そんな介護者を休憩・息抜きさせるために、患者を一時的に預かるようなレスパイトケアも充実していなければなりません。そういうデイケア的施設は圧倒的に不足しています。
「在宅医療においては介護者のメンタルケアも大事なんです。信頼する医師に聞いてもらえるだけで不安感が取れるということもあるんです。介護者を診るというスタンスも重要です」
精神科医の和田秀樹さんは指摘します。確かに家に帰ってくることができた患者本人は病院よりもいいと感じることもたくさんあるでしょう。しかし、面倒をみる家族の負担は重くならざるをえません。家族も含めた支援態勢がなければ、いい在宅医療を実現することはできません。下手をすれば介護者共倒れにもなりかねません。
家族からのサインに医療者がすぐに駆けつけられるのが理想
「介護保険は家族を介護から解放させるということが基本でしたが、やはり家族に頼らざるをえないというのが現実なんですね。家族に技術を教えてやってもらう。その中で、いつもと違うぞというサインを見つけたら連絡してもらい、フットワークのいい医療者がすぐにそこに駆けつける。それが理想の姿だと思います。私たちの地域ではだいたいそういうことができる態勢ができていますよ」
太田さんは胸を張ります。そして、医療者の中にも在宅医療の本質を理解できていない人が多いことの問題点を指摘します。
「在宅医療の方が医療の質が低いと思ってる人もいるようですが、それはとんでもない誤解です。病院でできて在宅でできないものは何か。確かにMRIや手術は在宅ではできません。しかし、それ以外のことはたいがい在宅でもできると考えていいでしょうね。レントゲンはじめ、いろんな医療機器も今や小型化してポータブルになっていますから。要するに、我々医療者が人間、人生を診るぞという意気込みを持つかどうかにかかっていると思いますよ」
「人生を診るぞ」という意気込みを持った医師がどれだけいるんでしょうか? そしてまた、そういう医師を育てる医学教育が行われているんでしょうか?
時代のニーズが在宅医療にあることは疑いようのない事実です。しかし、それに対応するべきシステムの構築、意識の変革、人材の育成は全くといっていいほど、進んでいません。のんびりと構えている余裕はありません。大胆でスピード感あふれる医療難民対策が今こそ、求められているのです。