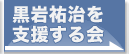
HOME > これまでの著書・コラム > NURSE SENKA
生理食塩水と誤って消毒液を点滴した8年前の医療事故
医療紛争を裁判によらない方法で解決しようという動きについて、この欄でもご紹介してきましたが、その中で「医療裁判でたとえ勝訴しても満足感は得られない」という話がありました。今回はそんな遺族の思いを直接、伺うことができました。
平成11年2月に都立広尾病院で起きた生理食塩水と誤って消毒液を点滴して患者が死亡するという事故がありました。死亡した永井悦子さんは看護師で、看護教務官として多くの看護師を育ててきました。亡くなる1カ月前に起きた横浜市大病院の患者取り違え事件に対して、「看護の基本は三度の確認、それができてないからあんなことが起きる」と怒っていたといいます。まさか自分の身に同じようなことが起きるとは夢にも思っていなかったことでしょう。
悦子さんは左手中指の関節リウマチの手術を受けましたが、手術は成功し、経過も順調でした。その翌日、処置室で事故は起きました。悦子さんのトレーに置かれていた隣の患者さん用の消毒液が入った注射器に、看護師が生理食塩水用のラベルを間違って貼ってしまったのです。
体内に1cc入った段階で、悦子さんが「気持ちが悪くなった」と訴えたため、いったん点滴は中断され、当直医が呼ばれました。その時の悦子さんは顔面蒼白、呼吸も弱く、意識レベルも低下し始めていました。医師は救命処置準備のために薬剤を注入しました。ところがここで決定的なミスを犯してしまったのです。
点滴用に確保していた静脈ラインをそのまま使って薬剤を投与しました。そのため残っていた消毒液9ccがすべて体内に入ってしまったのです。医師もまさか消毒薬が点滴されていたなんて思いもよらなかったでしょう。しかし、点滴中に具合が悪くなっているのですから、点滴そのものに問題があるのではと疑うのは医師としては当然のことでした。新たなラインを別にとって、そこから注入するべきでした。
かつて消毒液4ccを間違って点滴したという医療事故がありましたが、その際は死亡に至らずにすみました。それだけにここでの医師の処置ミスが決定的となったといえそうです。結局、その後、悦子さんは一気に心肺停止になってしまいました。
本当に体験したことが全然明らかにならず裁判は恐ろしい
夫の裕之さんは何が起きたのか、知る由もありませんでした。いきなり告げられた妻の死に動転する中で病院側からは次のように説明されました。
「点滴直後に急変し、その後心肺停止になってしまった。蘇生できなかったのは申し訳ない。死因としては心筋梗塞、大動脈解離、くも膜下出血などが考えられる。病理解剖を承諾してほしい」
医療ミスの可能性については一切触れられていませんでした。
その日の午後の2回目の説明では「間違えたかもしれない」という言葉はあったものの、あいまいなままに病理解剖が行われました。
ところが2日後、通夜の前に自宅で湯潅をしたところ、悦子さんの腕のすべての静脈が異常なドス黒い色となって浮かび上がったのです。真っ白い腕にたくさんの太い筋が走っている様は明らかに異様でした。血管の中に異物が入ったのは間違いないと、裕之さんは確信しました。
半年後、調査報告書がまとまり、石原都知事がミスを認め、謝罪の言葉を口にしました。都の衛生局長も自宅まで謝罪に来ました。しかし、ついに病院側からの謝罪の言葉は一切なかったといいます。「警察にも届けられていない。これではウヤムヤにされるだけだ」と危機感を抱いた裕之さんはついに刑事告訴に踏み切りました。
1年半後、東京地裁は看護師2名と院長に有罪判決を出しました。裕之さんは勝訴したわけですが、その時の気持ちを次のように語ってくれました。
「裁判というのはある意味で恐ろしいというか。僕は本当に体験したことが明らかになると思ったのが、全然明らかになりませんでしたね。むしろ僕の方がウソを言ってるかのように疑われました」
色分けや接続径など事故の教訓を活かす改善策が次々と
看護師の最初のミスが重大だと判断され、有罪となりましたが、裕之さんは病院の構造的問題にもっと踏み込んでもらいたかったといいます。処置室で患者一人一人のトレーになっていなかったこと。消毒液と体内に入る薬剤を同じトレーに載せることが日常的に行われていたこと。当直医が整形外科医であって、循環器系の医師を呼ぶ手段もなかったこと。そしてなによりも問題が起きた時に、謝罪をしようともせず、隠蔽しようとした病院スタッフの体質。
それらがどこまで反省されて、病院の安全管理の面で前向きの改善策につながったのか、裕之さんは納得できないことばかりでした。
「医療側が最初から真実を言ってくれたら、お互いが後々になっても話ができるようになると思うんですね。それが刑事裁判や民事裁判になってしまうと完全に敵対心になって、話などできる関係ではなくなってしまうんです。看護師さんたちは今も命日には花を贈ってきたりしますが、他の人たちは本当にどう感じているのかなと思うんですけどね。ずっと胸の内につかえたものがあるっていう感じです」
東京都ではこの事故を契機として毎年、医療事故の起きた2月の1週間を医療事故防止対策推進週間としているといいます。都の病院経営本部サービス推進部副参事の戸田武夫さんは、改善策は取られていると強調しました。
「あの事故以来、注射目的とそれ 以外のものは色で区別するようにしましたし、三方活栓も誤って接続できないように取り口の径も替えました。注射薬を準備した後は一患者一トレーにし、注射を実施する時に持参するようにもしました。医療器具の設定を変更した場合は、医師・看護師でダブルチェックをするようにもしました」
事故の教訓を活かそうという努力は確かに行われていました。しかし、遺族にはそれが的確には伝わっていませんでした。コミュニケーションが切れてしまった間柄ではそれもやむをえないのかもしれません。医療事故に対して被害者と加害者が共に向き合って乗り越えていくためには、やはり裁判によらない紛争解決法こそ有効なのだということを、この事件は私たちに教えてくれているようです。