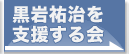
HOME > これまでの著書・コラム > NURSE SENKA
川崎協同病院事件の被告の医師に聞く“殺人行為”の実態
終末期医療のあり方に一石を投じた川崎協同病院事件はまだ我々の記憶に新しいところです。1998年、喘息の重症発作で入院していた男性患者の気管チューブを抜いた上、筋弛緩剤を投与して死なせたとして、担当していた医師は殺人罪に問われました。美人医師による密室殺人ということで、連日メディアを賑わしました。
2007年2月の東京高裁は、須田セツ子被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。一審より軽くなったとはいえ、殺人罪が認定されたことに変わりはありませんでした。しかし、この事件は本当に私たちがイメージする“殺人”の名に値するような事件だったのでしょうか? 私にはいまひとつ信じられないという気持ちが払拭できませんでした。
今回はその当事者の医師本人をゲストに迎え、“殺人行為”とされた実態をお伺いしました。
私が最初に疑念を抱いたのは、病院を去った彼女が今、地元で評判の「いい先生」として地域医療の最前線で活躍している現状を耳にしたことがきっかけでした。患者たちは口々に言います。「すごく丁寧で親切でいいと思いますよ」「優しい方ですよ。なんでも話しやすいし」。がんの末期の患者はテレビカメラに向かって懇願しました。「(裁判で)先生を取らないでください」。
患者たちが裁判のことを知らないわけはありません。殺人罪に問われている医師にあえて自分の身体を診てもらおうと思うのはどういう心情からなのでしょうか? 検察が何を主張しようが、裁判の結果はどうあれ、患者たちが彼女に寄せる信頼感に揺るぎがないことだけは間違いないようです。
私は殺人者というイメージとは程遠い須田医師について、さまざまに想像を膨らましていました。もしかしたら、病院内部における人間関係のもつれなどという医療とは無関係の背景があったのかもしれない。彼女は対立する人間にはめられただけなのかもしれない。しかし、たとえそうだとしてもなぜに筋弛緩剤などという薬を使ったのだろうか? それはやはり殺人行為と言われても仕方ないのか? 独断専行の側面もあったのだろうか? 私は自らの疑問を次々と彼女にぶつけていきました。
私が想像したとおり、彼女と対立していた麻酔科医の存在が浮かび上がりました。事件が表面化したのは患者さんが亡くなってから4年も後のことでした。
「今までふつうにやってきたのに突然あんたは殺人者だと言われました」
以前にこの病院を辞めさせられた医師がこの麻酔科医を外から使って、新聞に告発したのだといいます。組織の内部対立から問題が表面化することはよくあることです。私は自分が狙いを定めたとおりの状況だったことを知って驚きました。ただ、通常は内部告発で埋もれた事態が表面化することは、不正を摘発するための有効な手段です。しかし、この場合は不正が浮き彫りになったといえるのでしょうか?
患者の苦しみを除去するために筋弛緩剤を投与
カルテに筋弛緩剤を使用したという記述が残っていたことから、須田医師は殺人罪で内部告発されることになりました。こういう記述を残していることからもわかるように、彼女にはその行為が殺人罪で問われることもありうるという意識は全くなかったようです。
家族の見守る中、須田医師は気管チューブを抜きました。その直後、患者はえび反りになって苦しみ始めました。これは須田医師には想定外のことだったといいます。
「家族が10人以上見守る中でのことでしたから、みなさんにつらい思いをさせてしまったことはほんとうに申し訳ないと思います」
そこで、苦しみを除去しようとして鎮静剤を使いましたが、うまく効きませんでした。同僚の医師に相談したところ、筋弛緩剤のミオブロックを使うように勧められました。ただ、この時、その医師は再び挿管をするものとばかり思っていたようです。しかし、須田医師はあくまで苦しみを除去するために、筋弛緩剤を投与しました。
「脳中枢部がやられていると鎮静剤は効かないんですね。それで筋弛緩剤を使ったんですが、注射でパッと打ったんじゃないですよ。点滴で少量ずつ、調整しながら使いました」
この点について検察側は静脈注射を准看護師にやらせたとしており、主張は食い違っています。また、管を抜いたときも弁護側が家族から抜いて欲しいという申し出があったとしているのに対し、検察側は須田被告が「じゃあ、抜きますね」と言って抜いたとしており、食い違っています。
終末期医療の処置に殺人罪という言葉は果たしてふさわしいか
話を直接聞いてみて、確かに須田医師には脇の甘さがあったと言わざるをえないという気がしました。家族に対して「9割9分脳死状態です」と言ったといいますが、脳死判定もしていない状況で、そういう言い方をするのは軽率だったでしょう。
しかも私たちの事前取材に対しても、「救急でいらした時にはすでに死んでらしたわけです」という言葉を平気で口にしていました。おそらく蘇生はできたけれど「すでに死んでいる」というのが、彼女の基本的な認識だったのでしょう。厳密さを求められる死の判定において、少しアバウトすぎる危なさが見えたような気がしました。
しかし、彼女に殺意があったわけではないということだけは確かでしょう。殺意がなくても死なせたら殺人罪ということになることもあるのでしょうが、ギリギリの終末期医療の最前線での微妙な処置に殺人罪という言葉はやはりふさわしくないと思わざるをえませんでした。
管をつなぎっぱなしにしておけば、殺人罪に問われることはありえません。患者やその家族の気持ちに思いを致すことなどしなければ、機械的にそうしておけばいいのです。しかし、そういう状態が長期化することでの家族への負担、患者本人がそれで幸せなのかなど、あれこれと心を配り始めると、最期をどうしていくかという課題は出てきます。
終末期に関するガイドラインはまとめられましたが、それで解決とはいかないようです。医師に対する刑事訴追はよほどのことでないかぎり行わないということにしなければ、逆に心の伴わない終末期医療が増えてしまうような気がします。殺人罪に問われる恐怖から医療の現場を解放することが医療崩壊の流れを止める一つのカギではないかと思いました。