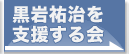
HOME > これまでの著書・コラム > NURSE SENKA
母親は病気の兄にかかりきりになり置き去りにされる妹
今回の番組は、私が客員教授を務める国際医療福祉大学の大学院の授業の一環として制作したものです。院生で助産師でもある三ツ堀祥子さんの企画で「きょうだいが病気になった子供たち」というものでした。重い病気になった子供を抱えた親は、その子供にかかりきりになってしまいがちです。しかし、その陰で置き去りにされているきょうだいたちに目を向けなければいけないというのが三ツ堀さんの問題提起でした。
『おにいちゃんが病気になったその日から』という絵本も出版されています。これは病気のきょうだいがいて実際につらい経験をした人が書いた作品で、「僕は広いうちの中でひとりぼっち」「ママロボット」ときょうだいの孤独感を表現しています。
東京に住む島津理佳ちゃん(6つ)もそんな思いを体験した一人です。ちょうど彼女が生まれた頃、お兄ちゃんが小児がんに罹っていることが明らかになりました。当然のごとく、母親はお兄ちゃんのことで頭がいっぱいになり、理佳ちゃんよりもお兄ちゃん優先の毎日になりました。すると理佳ちゃんにさまざまな異変が表れ始めたのです。その当時の母親の保育日誌には次のように記されています。
「朝、パズルをしたら失敗して投げつけていました。本棚に行って本まで投げつけていました」
それはお兄ちゃんが退院した後も続きました。母親は言います。
「食器をバーンと投げちゃったりして、癇癪を起こしていました。家に帰ってくると、ぎゃあぎゃあ騒いじゃったりとかで、私も結構、混乱していました」
その後、お兄ちゃんの病気は治り、今では理佳ちゃんもすっかり平静さを取り戻すことができたそうです。
寂しさを言葉で語らず我慢しているサインを見落とさないこと
沖縄の伊佐愛ちゃんはお姉ちゃんのがんの発病がきっかけで、家族が別れ別れに住むことになりました。お姉ちゃんは東京の病院に転院し、母親は付き添いでついて行きました。愛ちゃんは父親と2人、沖縄に残されたのです。愛ちゃんはその当時のことを次のように振り返ります。
「がんって言われた時は本人のお姉ちゃんの方がつらかったと思うけど、自分もやっぱりつらかったですね。小学校の卒業式とかいろんな行事でも家族は来れなかったし、周りに相談する人とかいなかったから、つらいことが続きました。家族が一つになりたかったのかなって……」
当時、愛ちゃんと接点のあった茨城キリスト教大学看護学部教授の藤村真弓さんは言います。
「最初、お母さんは愛ちゃんももう小学校6年生で大きいから、そんなに心配してないって、おっしゃったんですね。でも、『そんなことはないですよ』と私はお母さんにお話ししたんです。隠してはいけない、お姉ちゃんの病気のことについて、本当のことを話した方がいいって申し上げました。お母さんとしては半信半疑だったようですが、実践されて、それから愛ちゃんも明るくなってきて、病室でお姉ちゃんと2人で楽しそうに話すようになったそうです」
きょうだいへの気配りを忘れないでいると、治療にも良い影響が出てくるのだそうです。愛ちゃんが元気になったことで、お姉ちゃんの症状も改善されてきたようです。愛ちゃんの母親は言います。
「妹と言葉をかけ合ったりというサポートは親ではできないことです。治療は病院だけど回復は家族だと思ってます」
アメリカのきょうだい支援プロジェクトのドナルド・マイヤー氏はきょうだいたちの陥りやすい心理状態について分析しています。「お姉ちゃんなんて死んじゃえばいい」と自己中心的発想をしたり、その逆に病気の子供に懸命になる母を気遣って「いい子でいなくっちゃ」と強く思いすぎてしまうこともよくあるそうです。
神奈川県立こども医療センターの児童思春期精神科部長の清家洋二さんは言います。
「子供は寂しさを感じていても言葉ではなかなか語らないので、そのサインを見落とさないようにすることが大事です。きょうだいが死んじゃえばいいと思った子供は、自分がそういう気持ちを抱いたことへの罪悪感に悩まされ続けることもあるんです。そういう思いが外に表れている子供はまだいいんですが、そうでない子供の方が心配です。後々になって精神的症状として出てくることもあるんです」
ナースが患者の家族に声をかけることはとっても大事なこと
きょうだいはいろんなことを我慢しているのだそうです。「自分の話を聞いてもらうこと」「自分のやりたいこと」「学校行事に来ること」「母が不在で寂しいこと」「病院外で家族と過ごすこと」「家族で食事をすること」。しかし、親から「あなたは元気なんだから我慢しなさい」と言われると、身の置き所がなくなってしまうのだといいます。
確かに医療者が意識するかしないかで大きく違ってくることではありますが、現実問題として医師もナースも忙しすぎて、なかなか家族まで目を向ける余裕がないのではないでしょうか? 精神科の医師があらゆる病気の子供のケースに積極的にかかわっていれば、フォローできるかもしれません。清家氏は言います。
「骨髄移植などの場合には、無菌室に入ることもあり、精神科の医師もチームの一員として最初から介入することはあります。しかし、病院全体で展開するのはなかなか難しいでしょうね。精神科医がかかわっても保険点数になりませんから、ただ単にサービスの提供になってしまいます」
精神科医の和田秀樹氏は、日本では病院の中における精神科医の相対的地位が低いがゆえに、精神科医も含めたチームがなかなか作れないのだと言います。
藤村さんはナースの役割を強調しました。
「家族支援をするのに最もふさわしいのはナースではないでしょうか? 医師よりも患者さんの身近にいるナースが、患者さんの家族に声をかけるということがとっても大事なことだと思いますね。きょうだいもお母さんも声かけてもらうだけで助かる場合がたくさんあるんです。そんな感性をもったナースを育てていきたいです」
患者のきょうだいにも目を向ける必要があるということを、医療者だけでなく我々一人ひとりが知るというだけでも大きな効果が期待できるに違いありません。そういう機会を与えるきっかけとなったわけですから、三ツ堀さんの初作品は意義ある番組になったといっても良いのではないでしょうか?